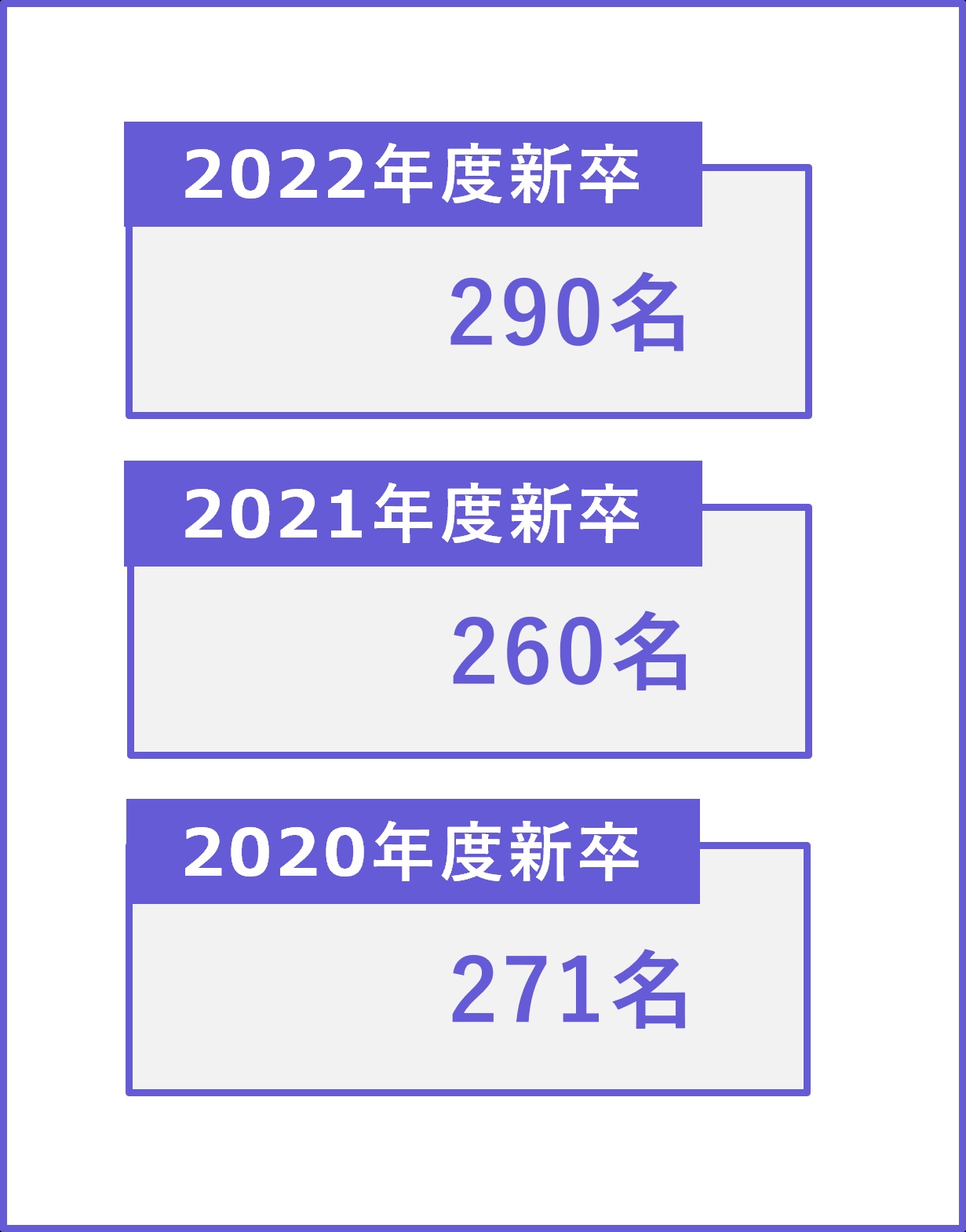本記事の内容
本記事では、TISの同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。
本記事の視聴対象者は以下の方です。
- TISに興味がある方。
- TISの選考を受ける方。
- 選考を通過するためにTISだけの志望動機を書きたい方。
- 他のSIerと差別化ができず困っている方。
- SIer業界に興味がある方。
YouTubeチャンネルはこちら
本記事では、TISの同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。
本記事の視聴対象者は以下の方です。
YouTubeチャンネルはこちら
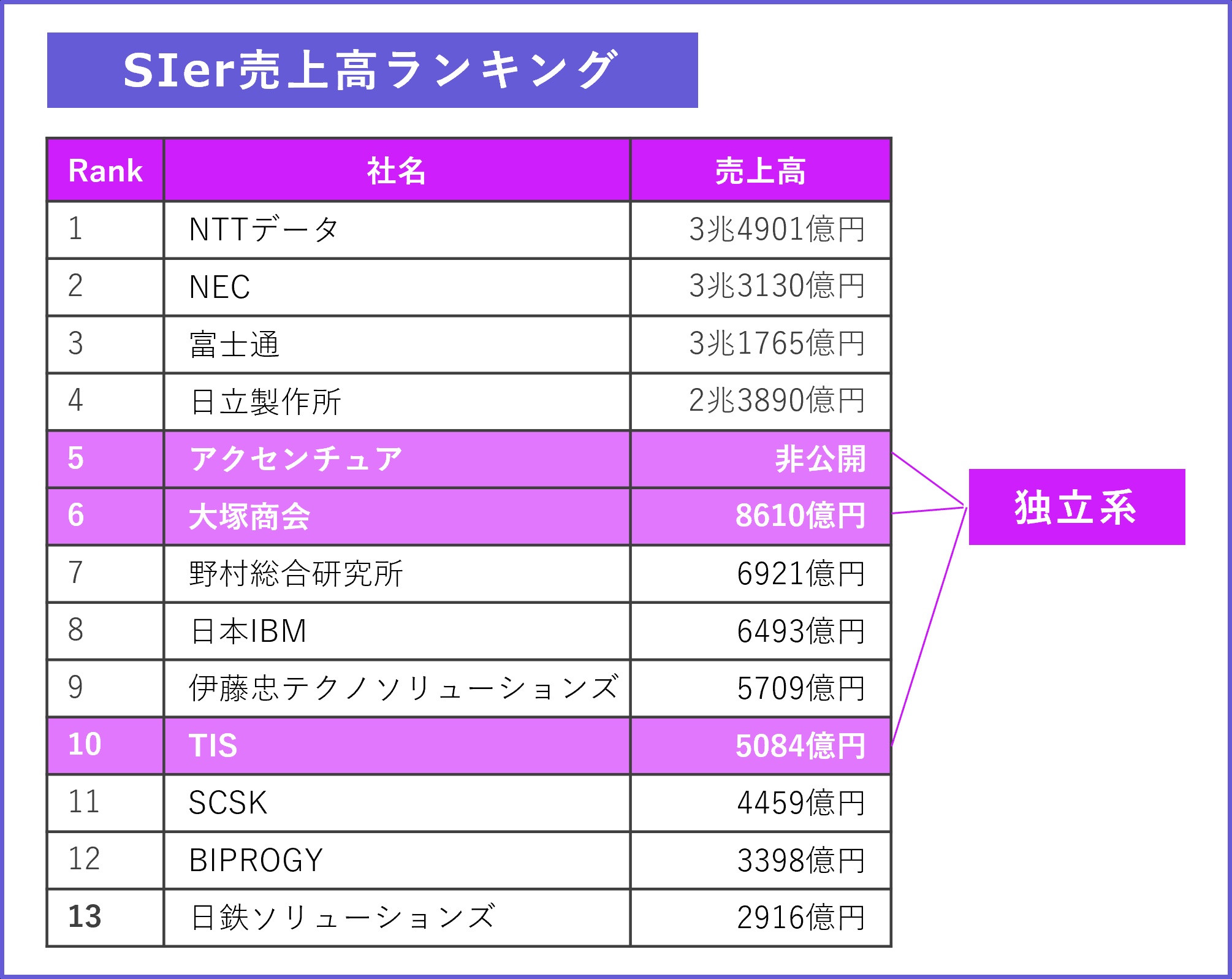


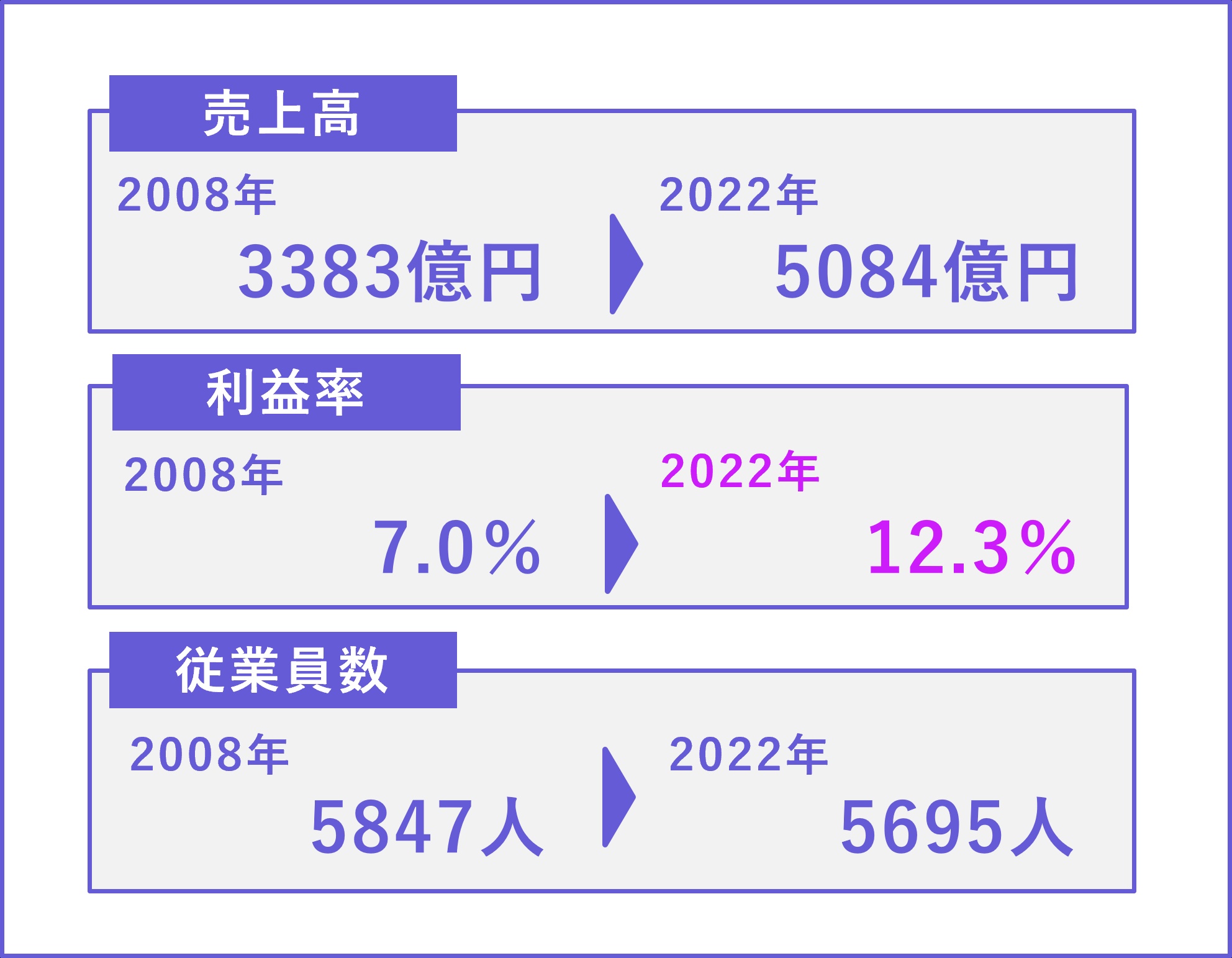
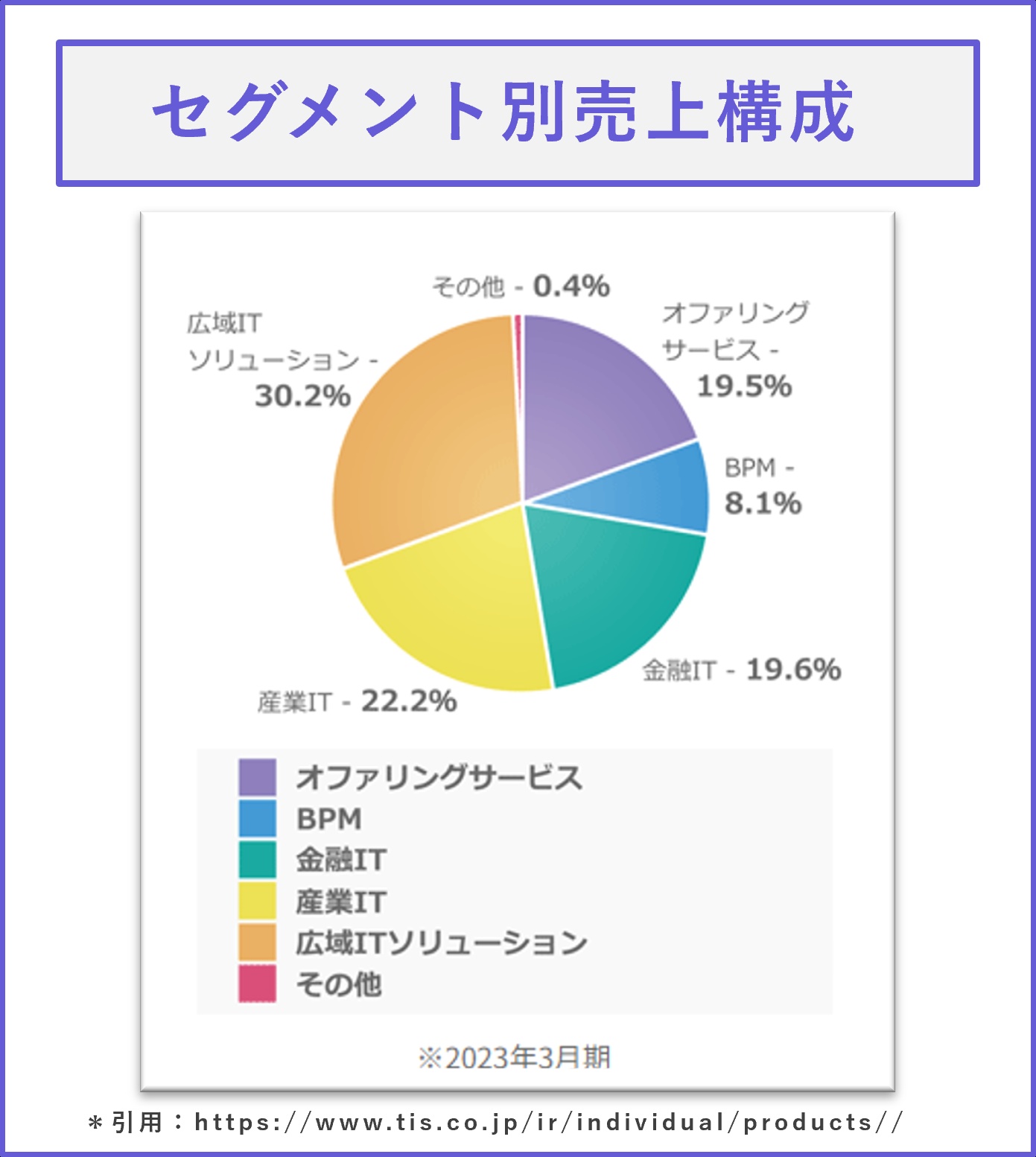
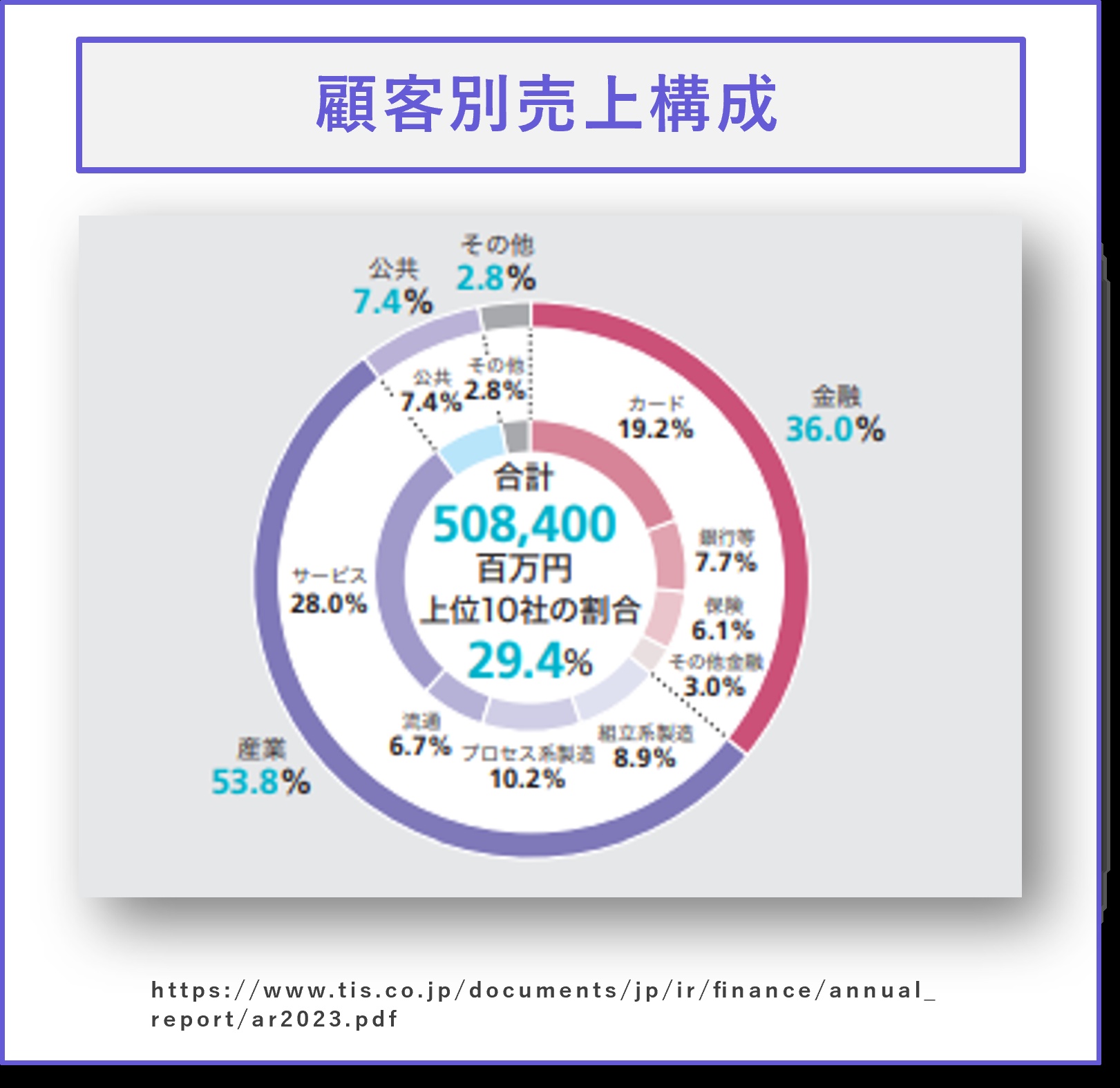
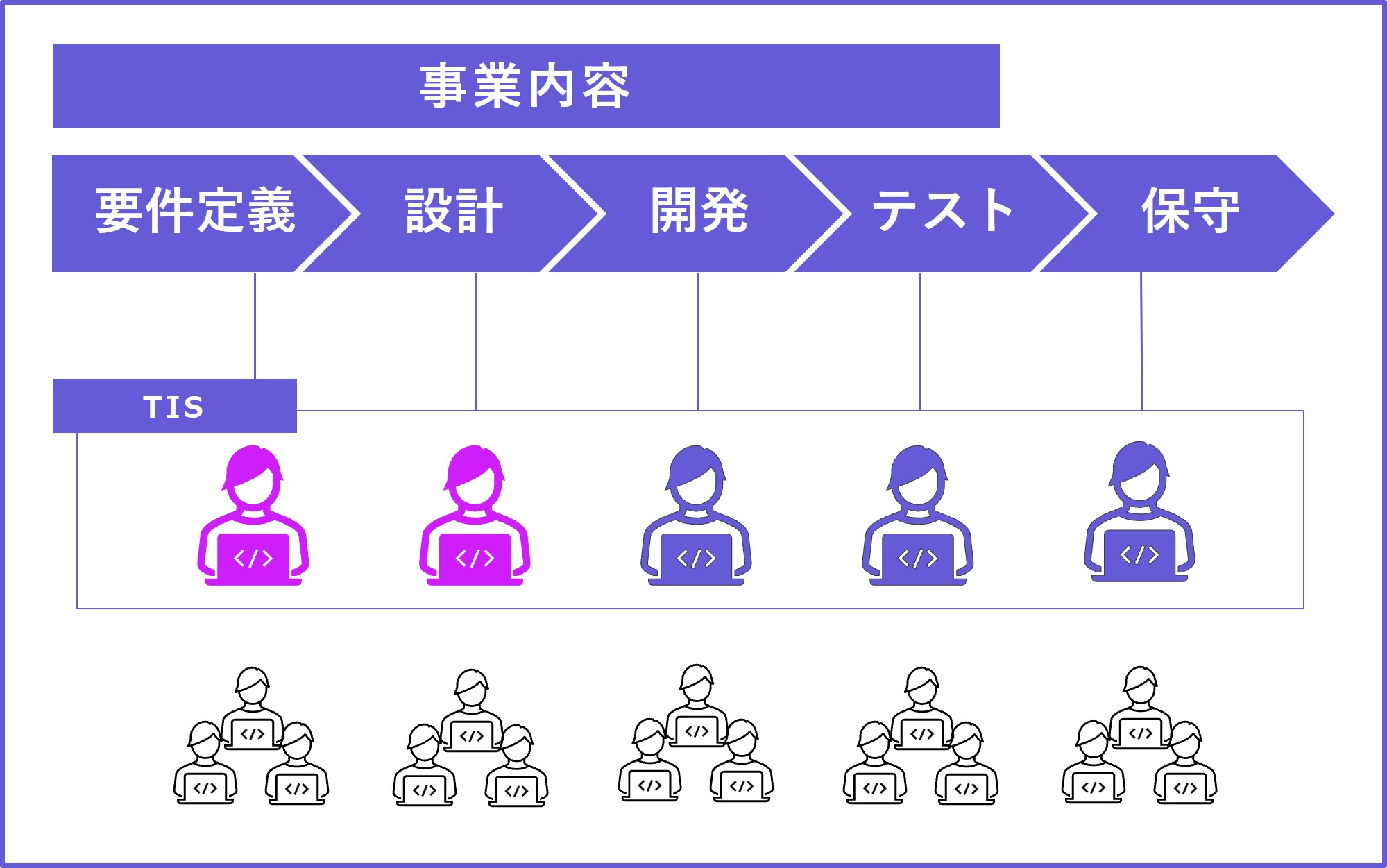
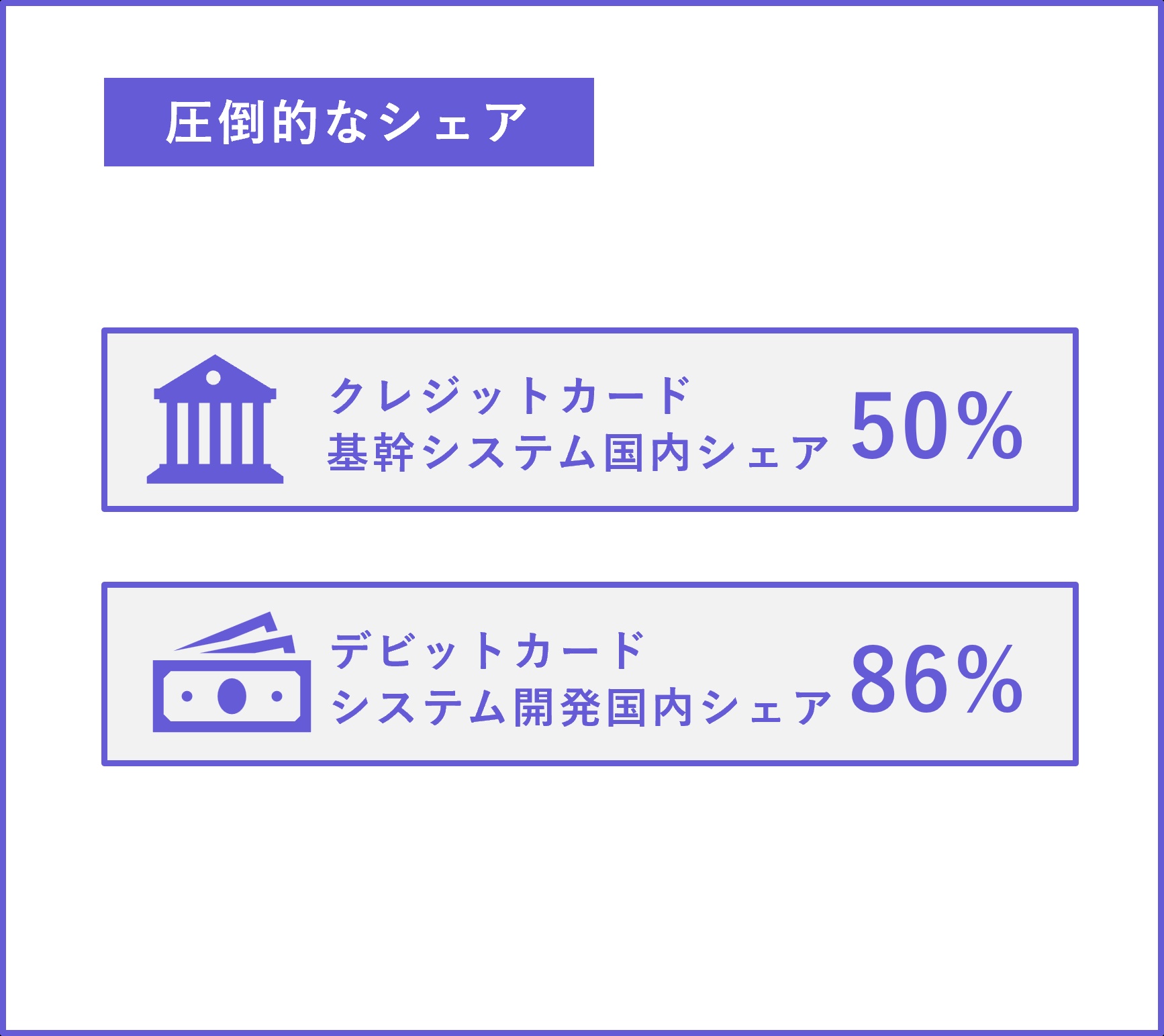
*基本的には超大手のSIer群が業界シェアを独占している。

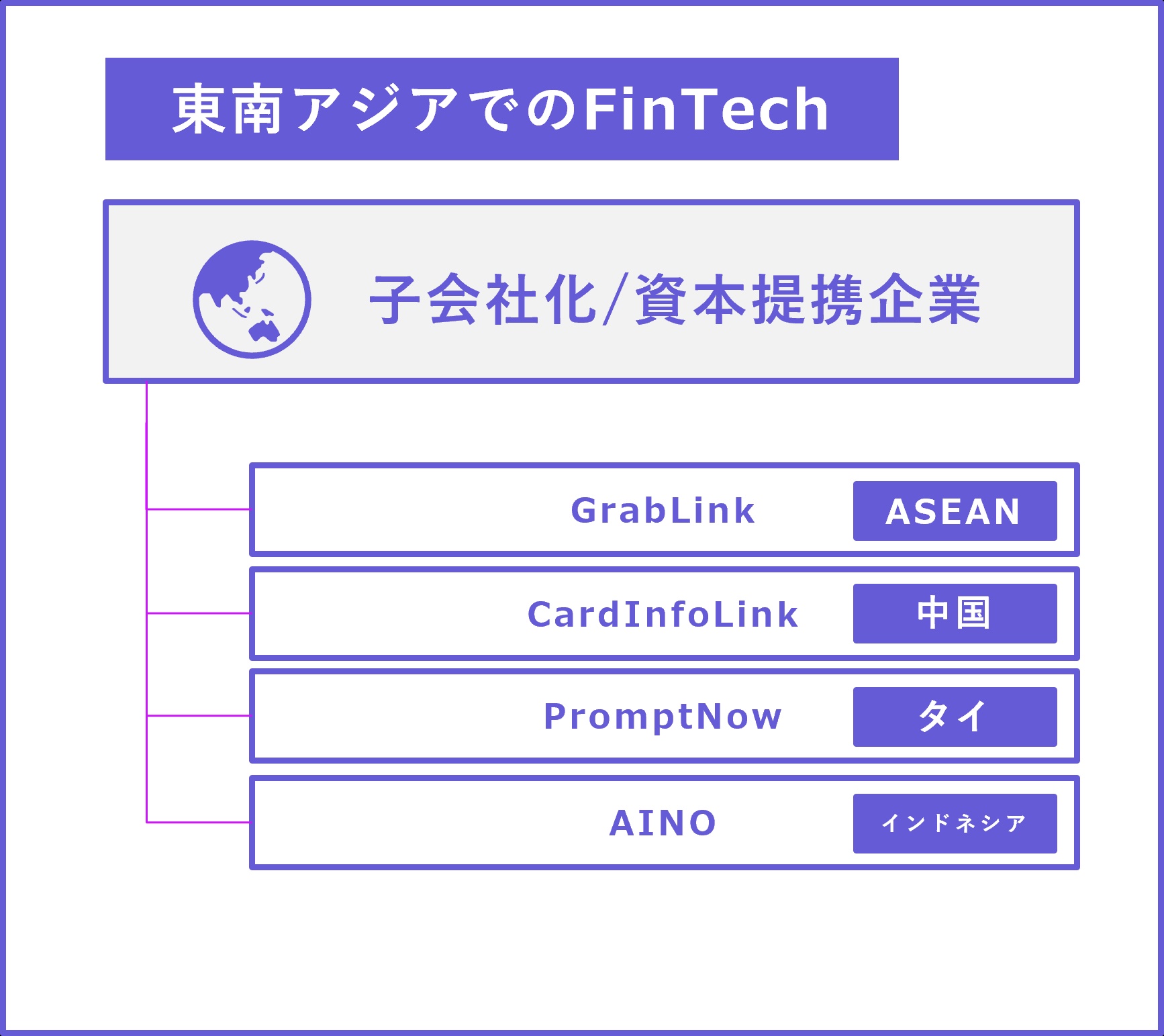
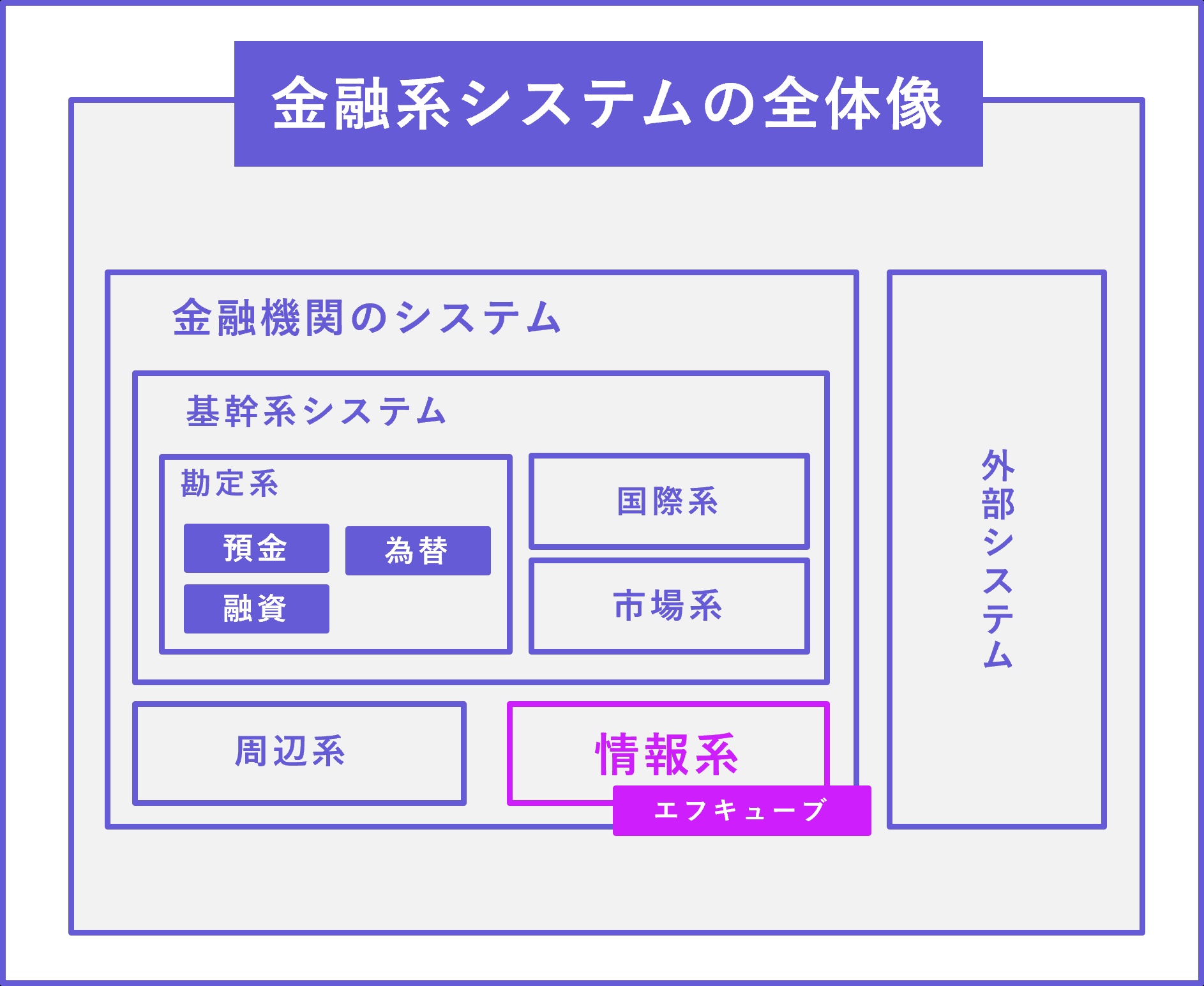

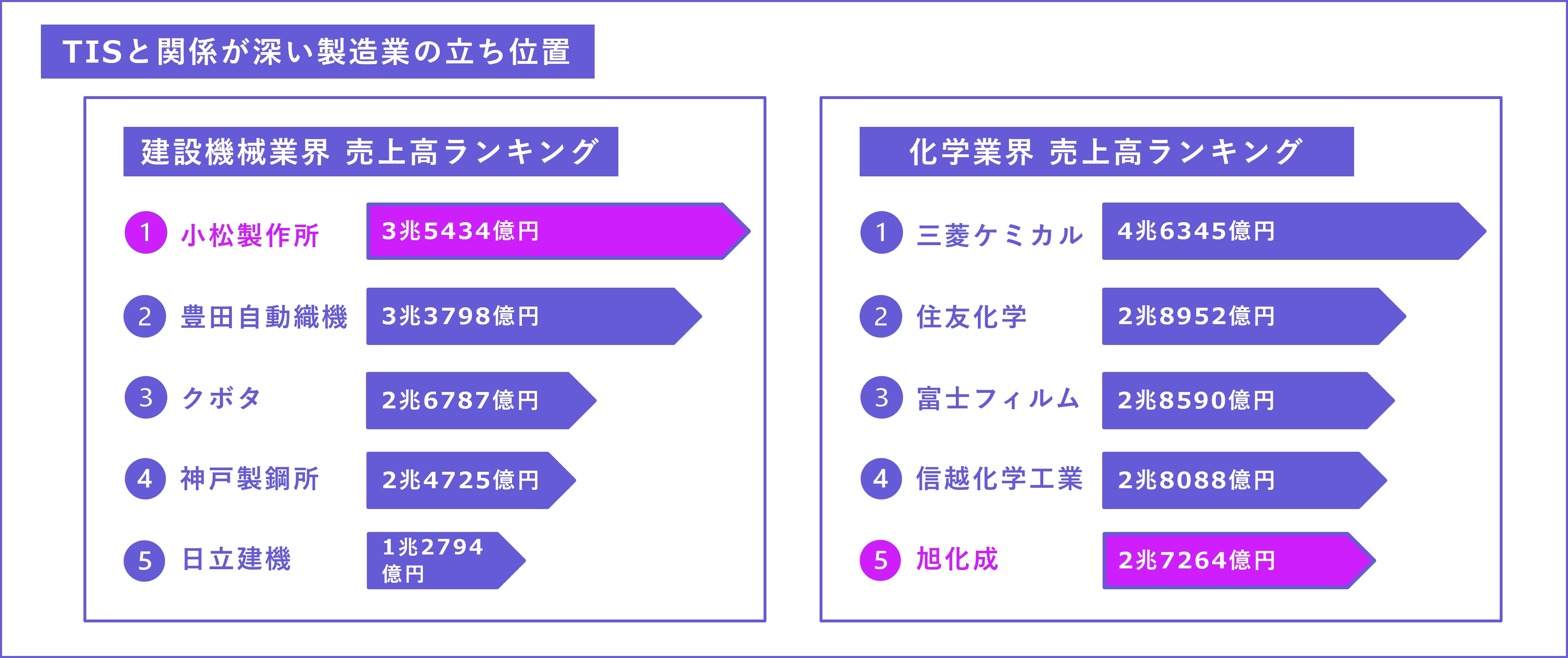
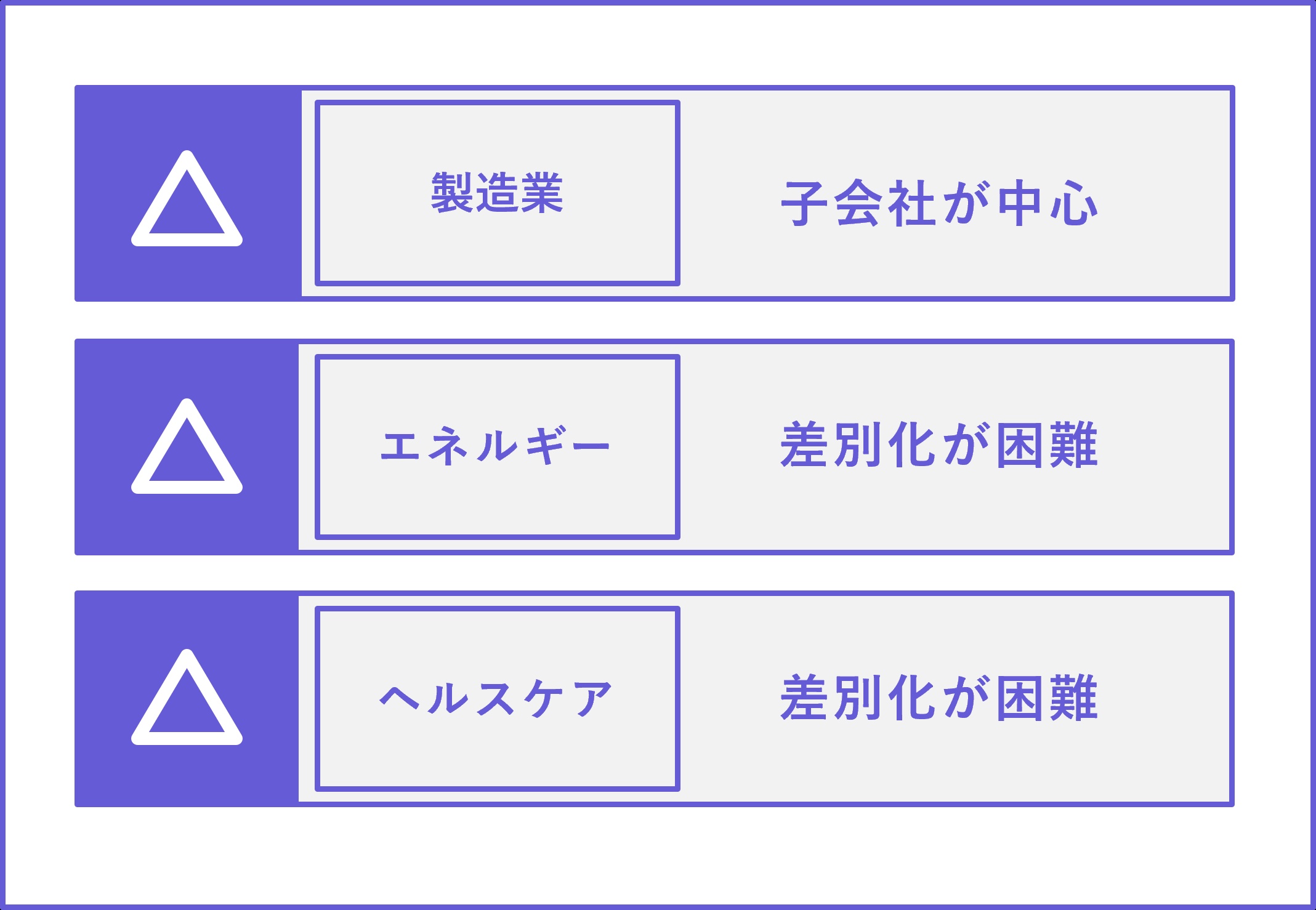
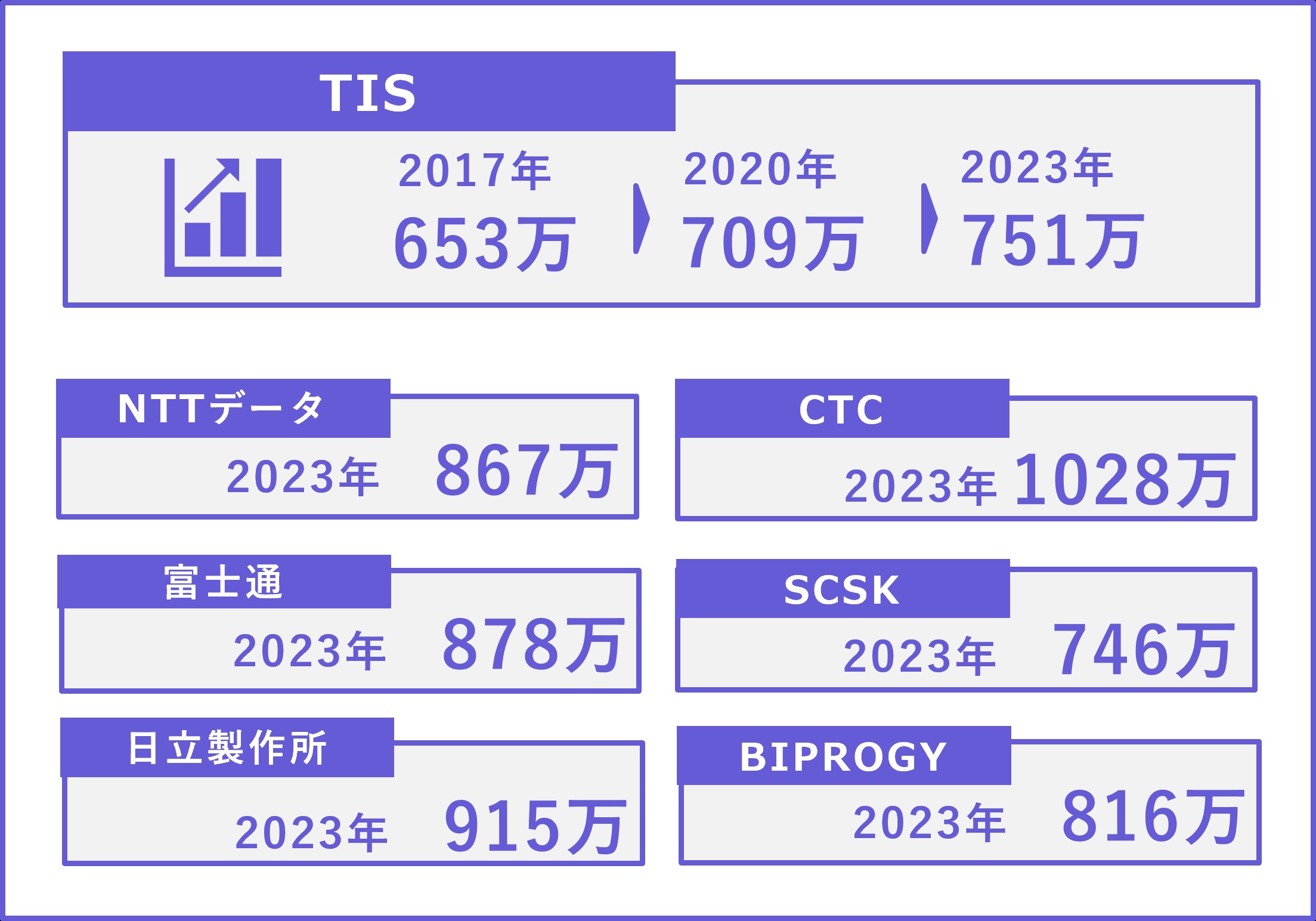
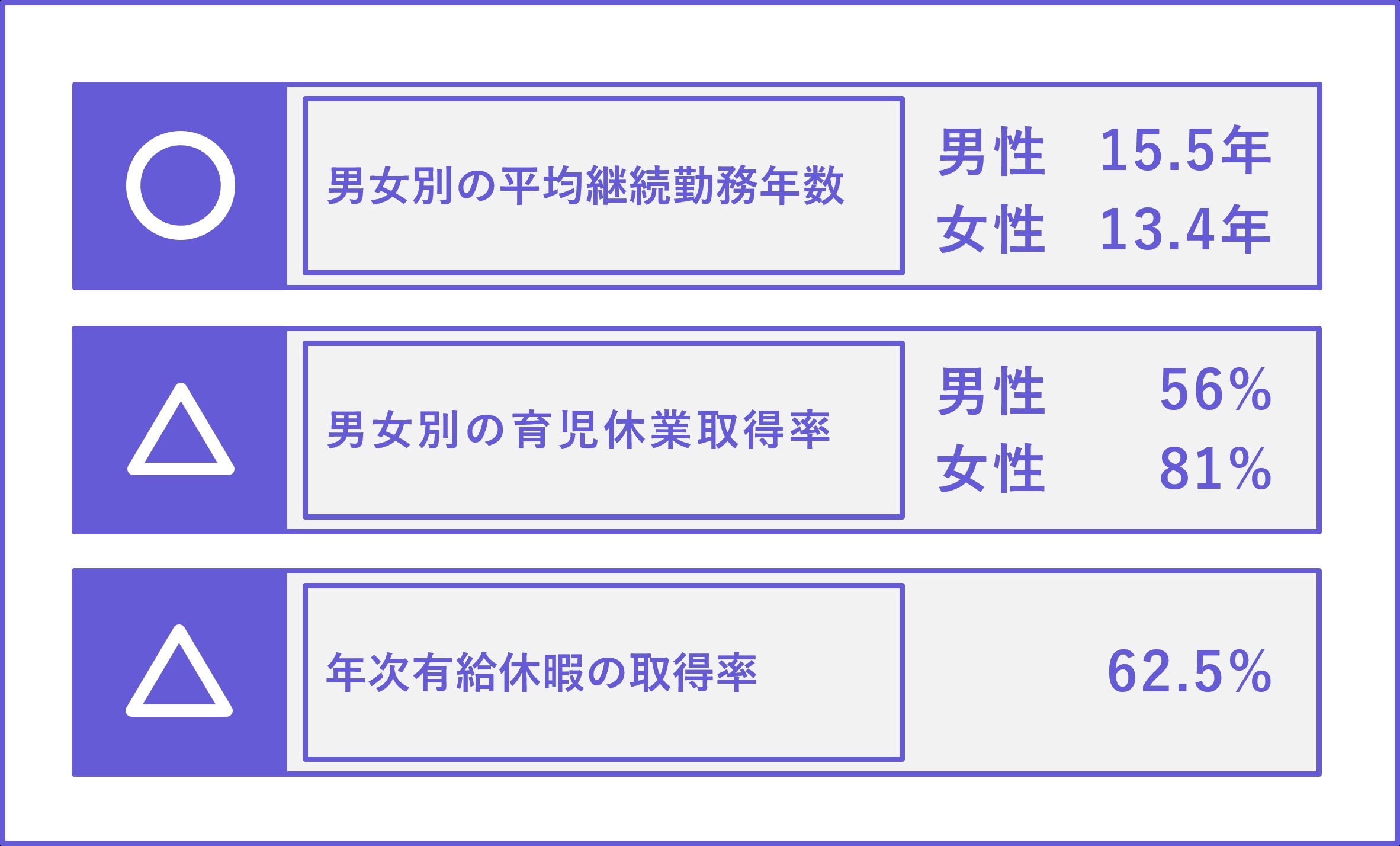
*大手SIer売上上位13社内の順位。