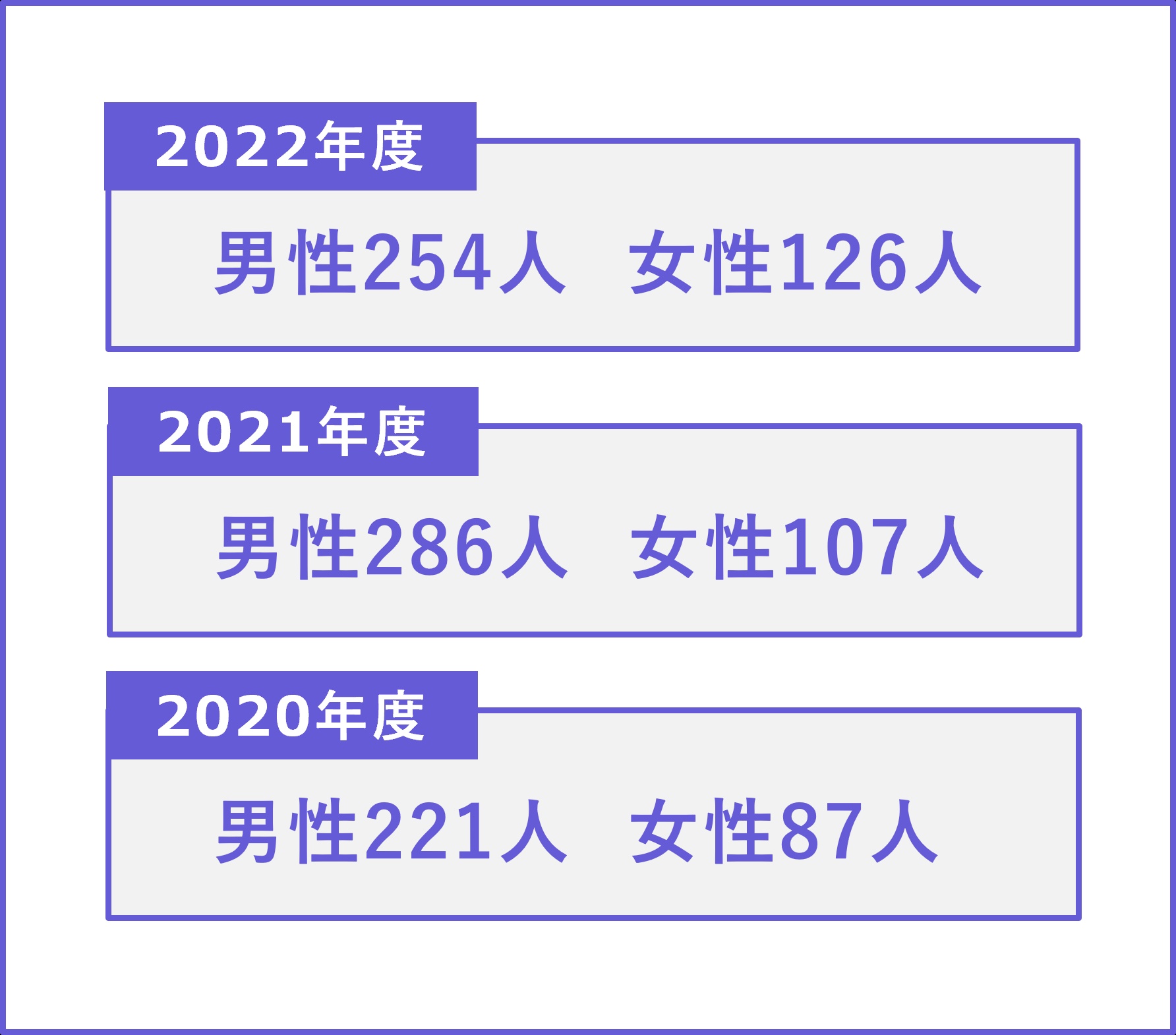本記事の内容
本記事では、野村総合研究所の同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。
本記事の視聴対象者は以下の方です。
- 野村総合研究所に興味がある方。
- 野村総合研究所の選考を受ける方。
- 野村総合研究所の詳細な企業分析を行いたい方。
- 他のSIerと差別化ができず困っている方。
- SIer業界に興味がある方。
YouTubeチャンネルはこちら
本記事では、野村総合研究所の同業他社と比較した強み、弱みを独自の視点で解説します。当サイトは、この分析を基に、選考を受けた全てのSIerで選考を通過しました。
本記事の視聴対象者は以下の方です。
YouTubeチャンネルはこちら
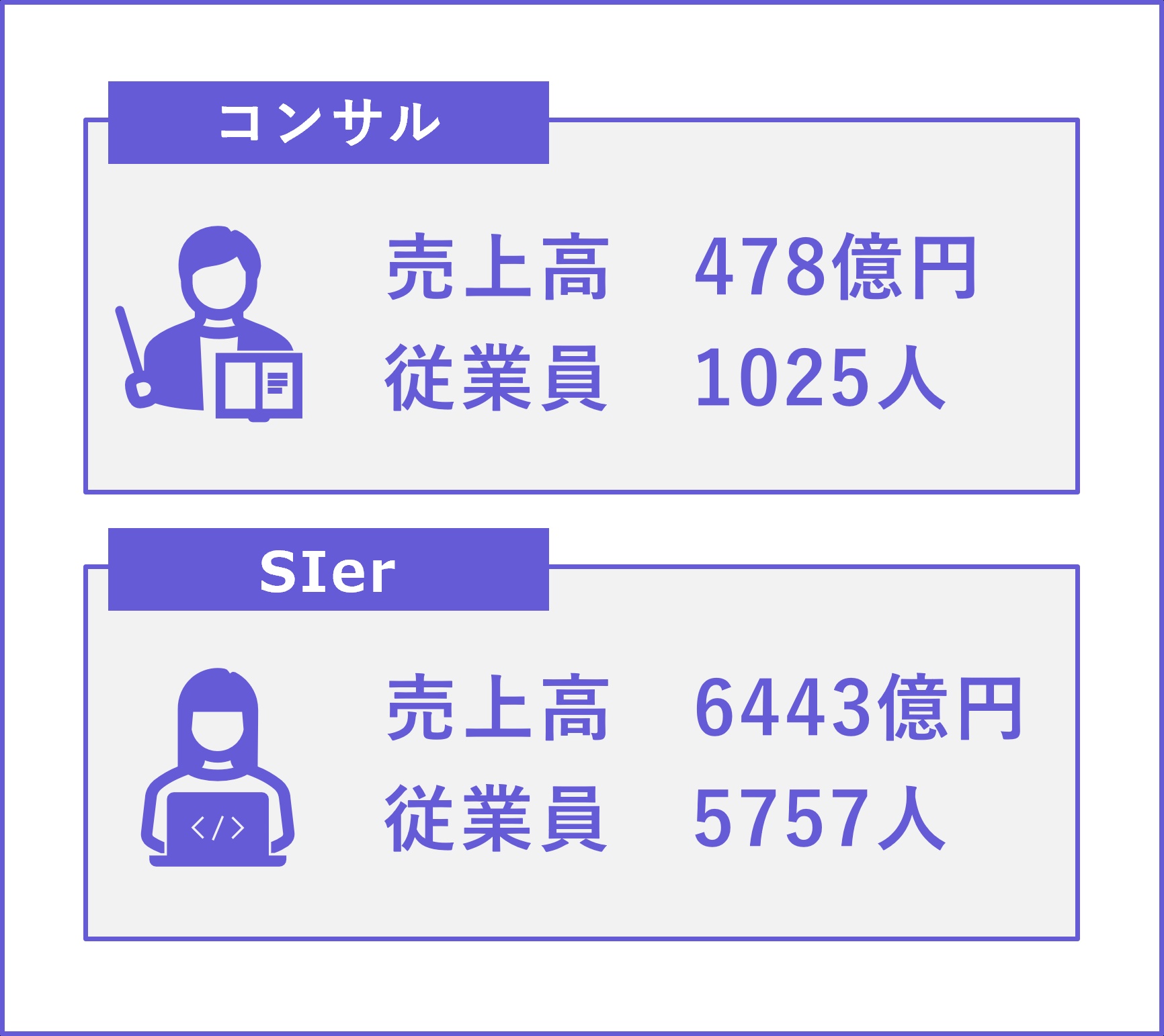
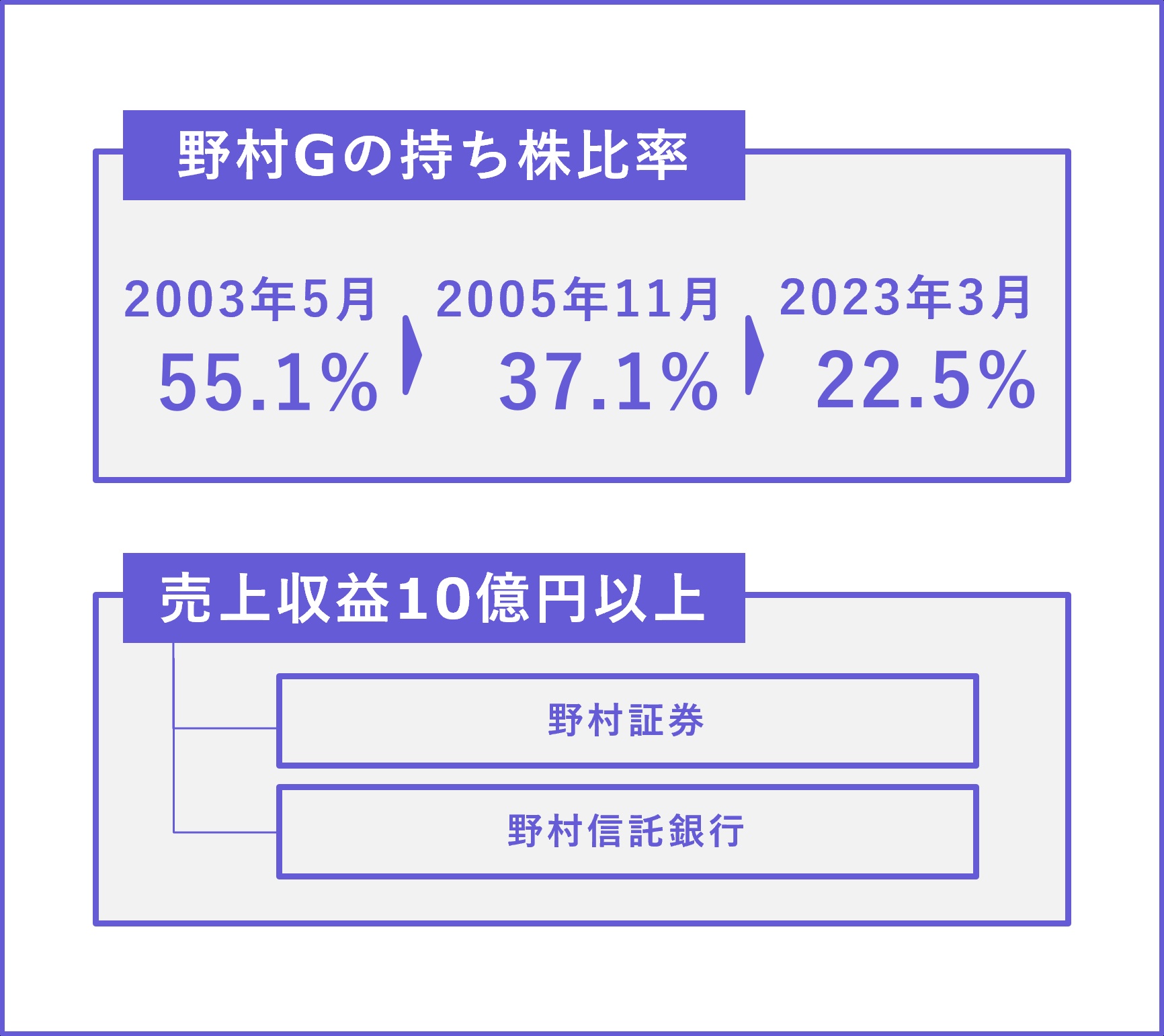
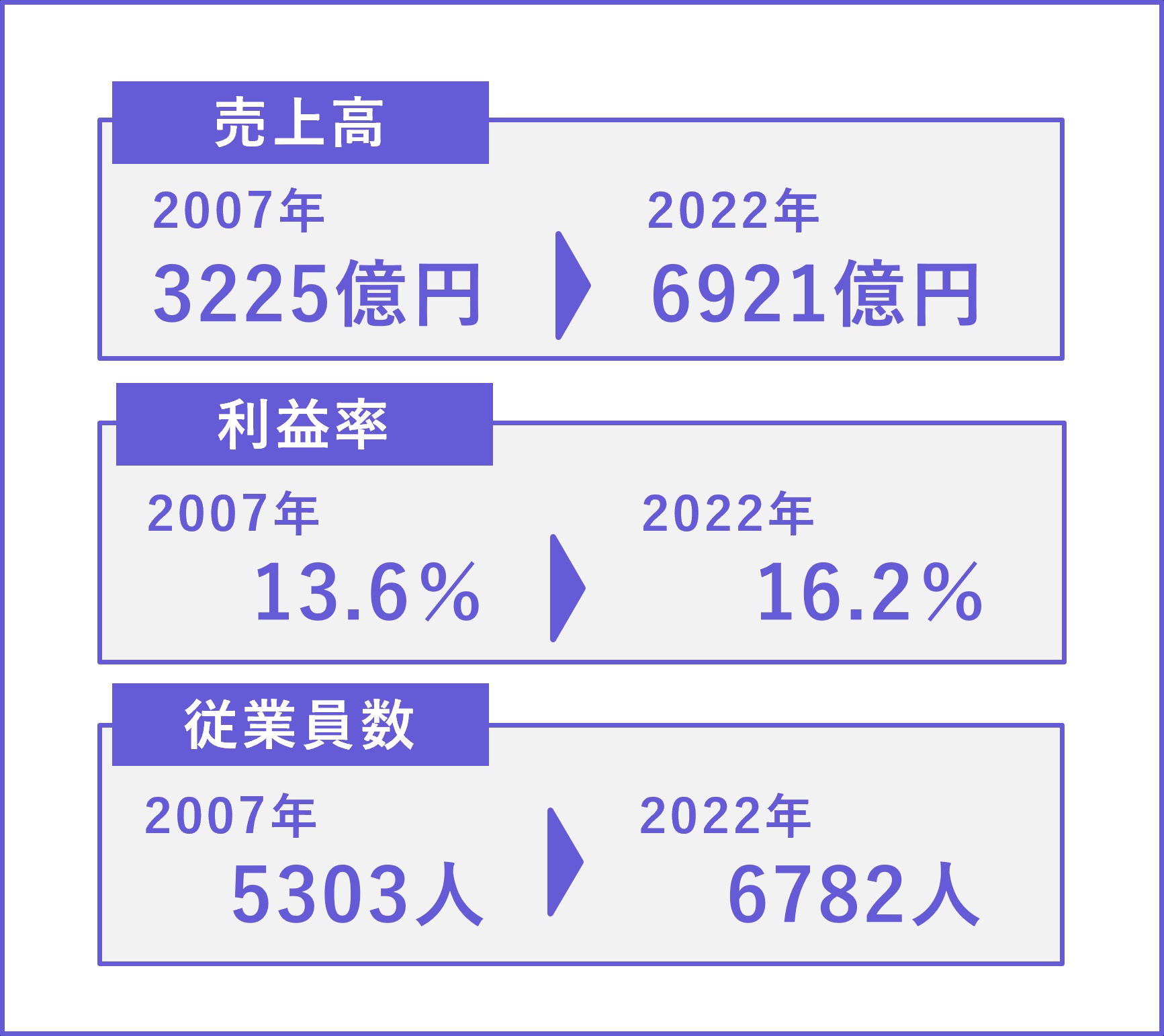
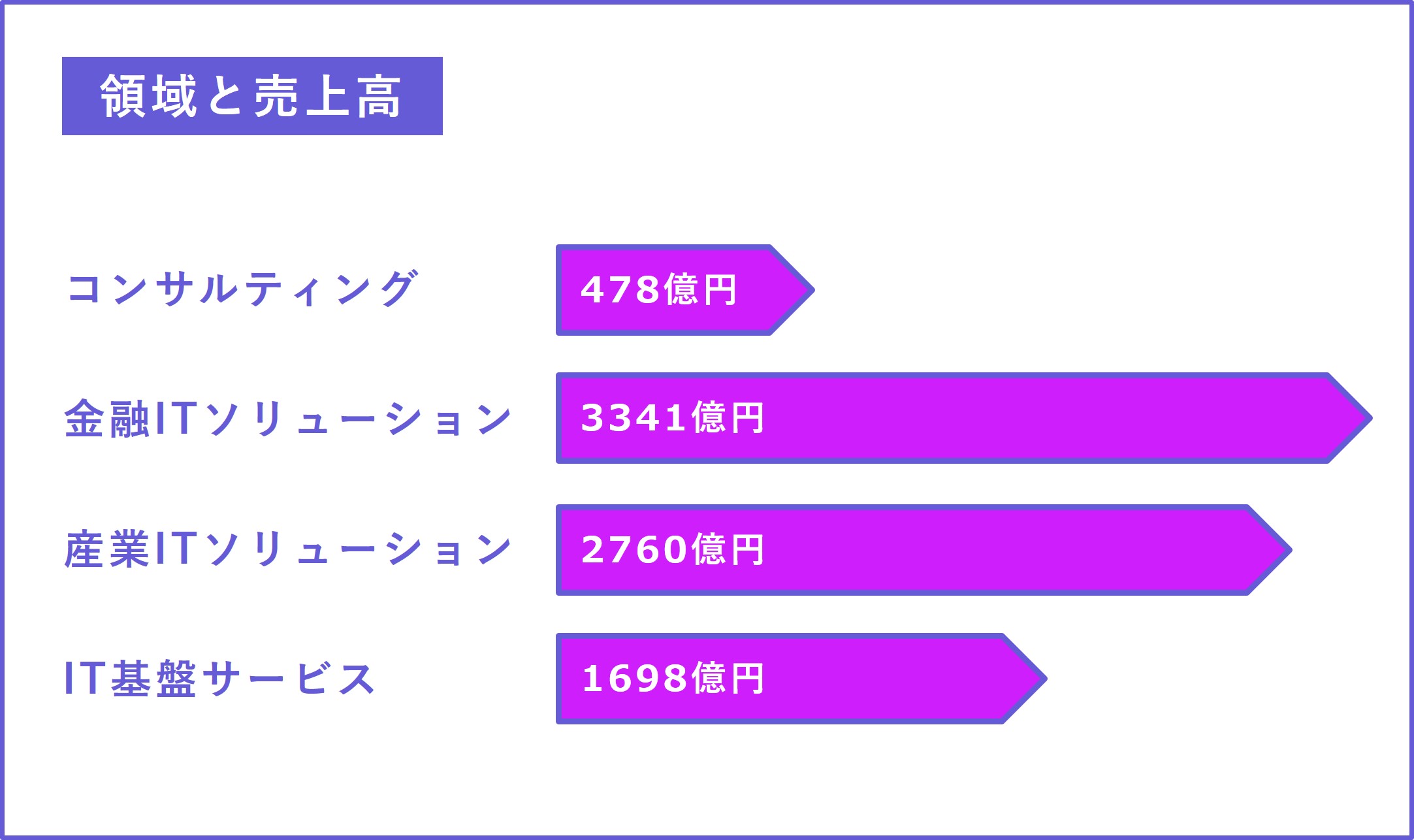
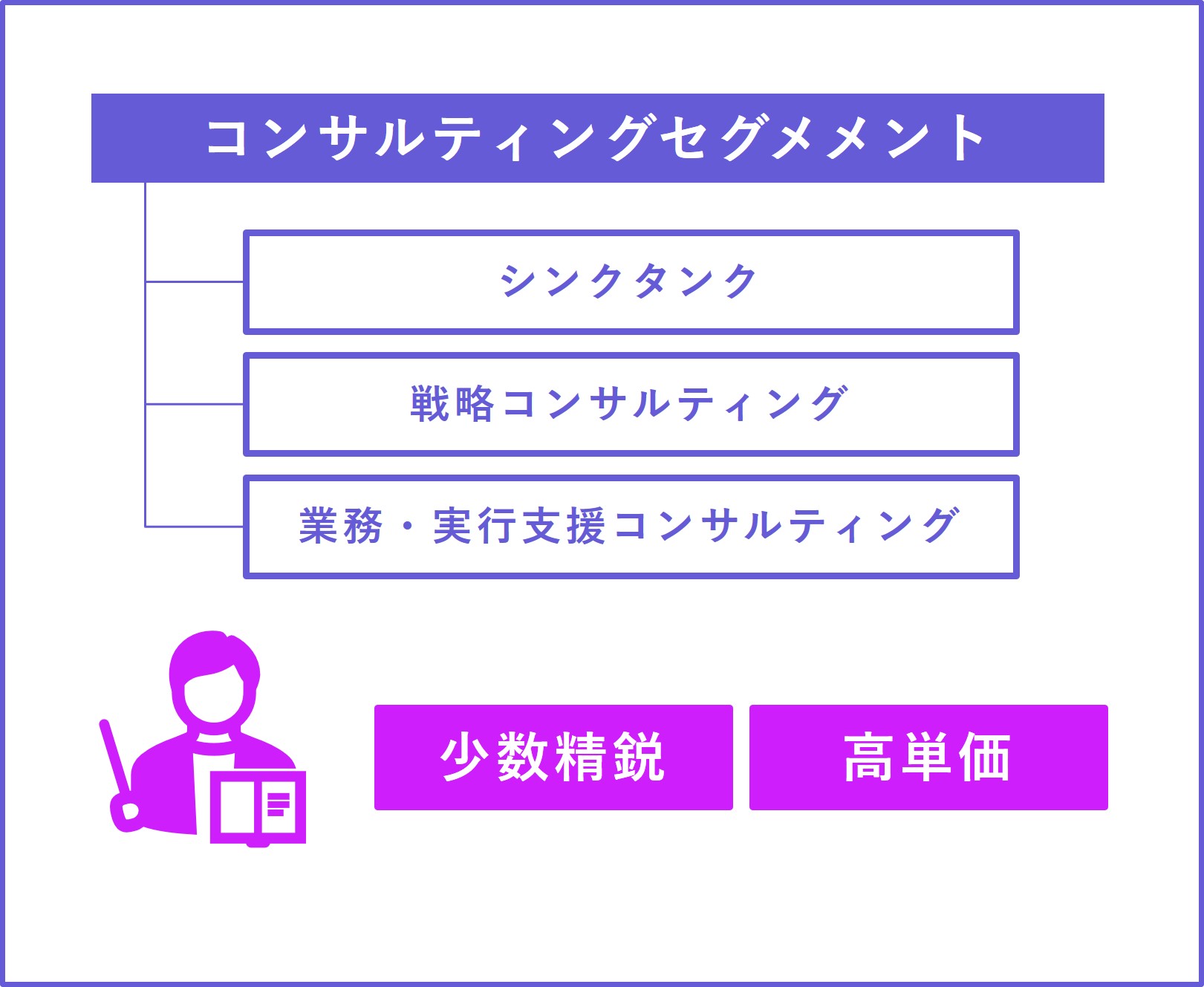
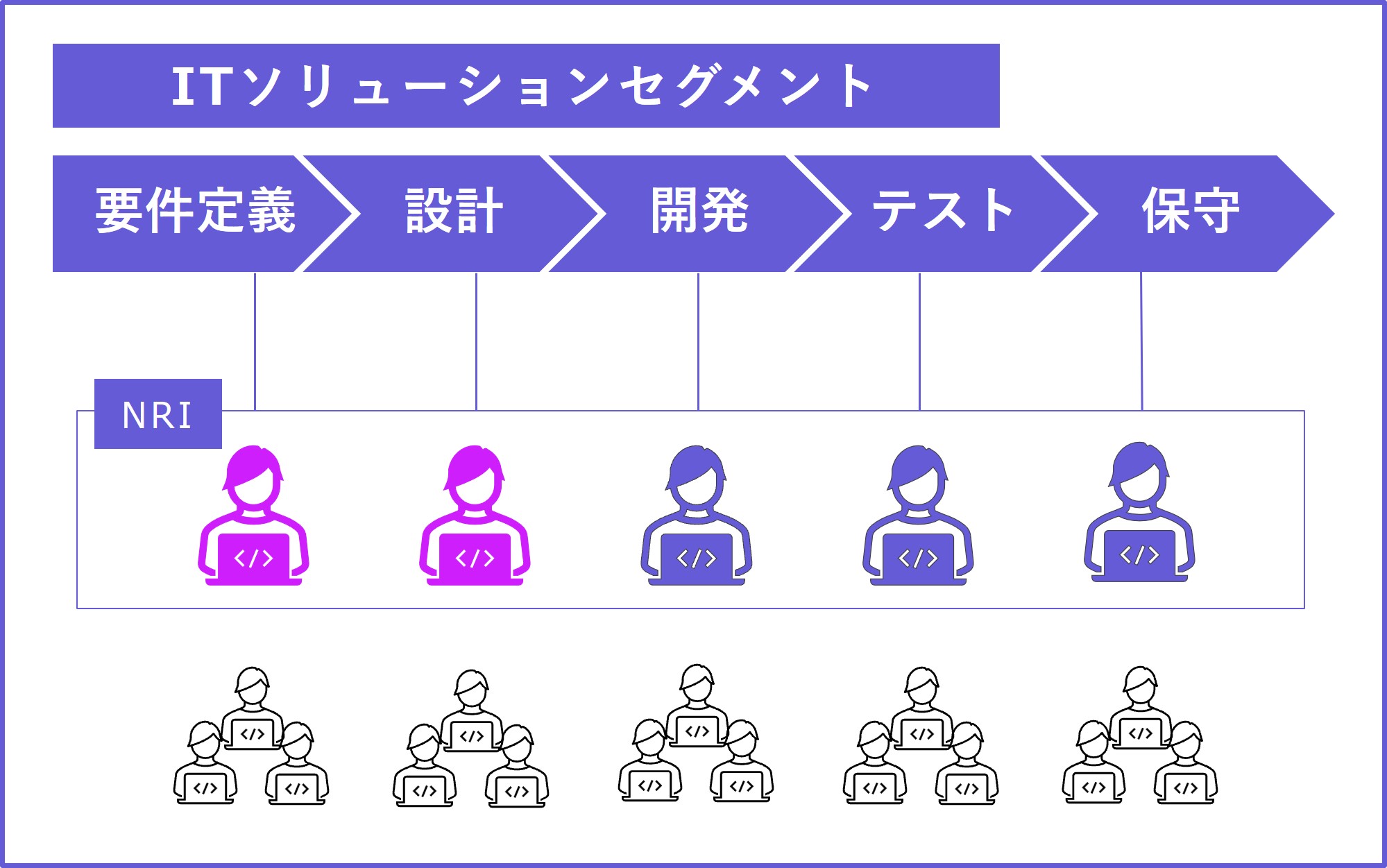
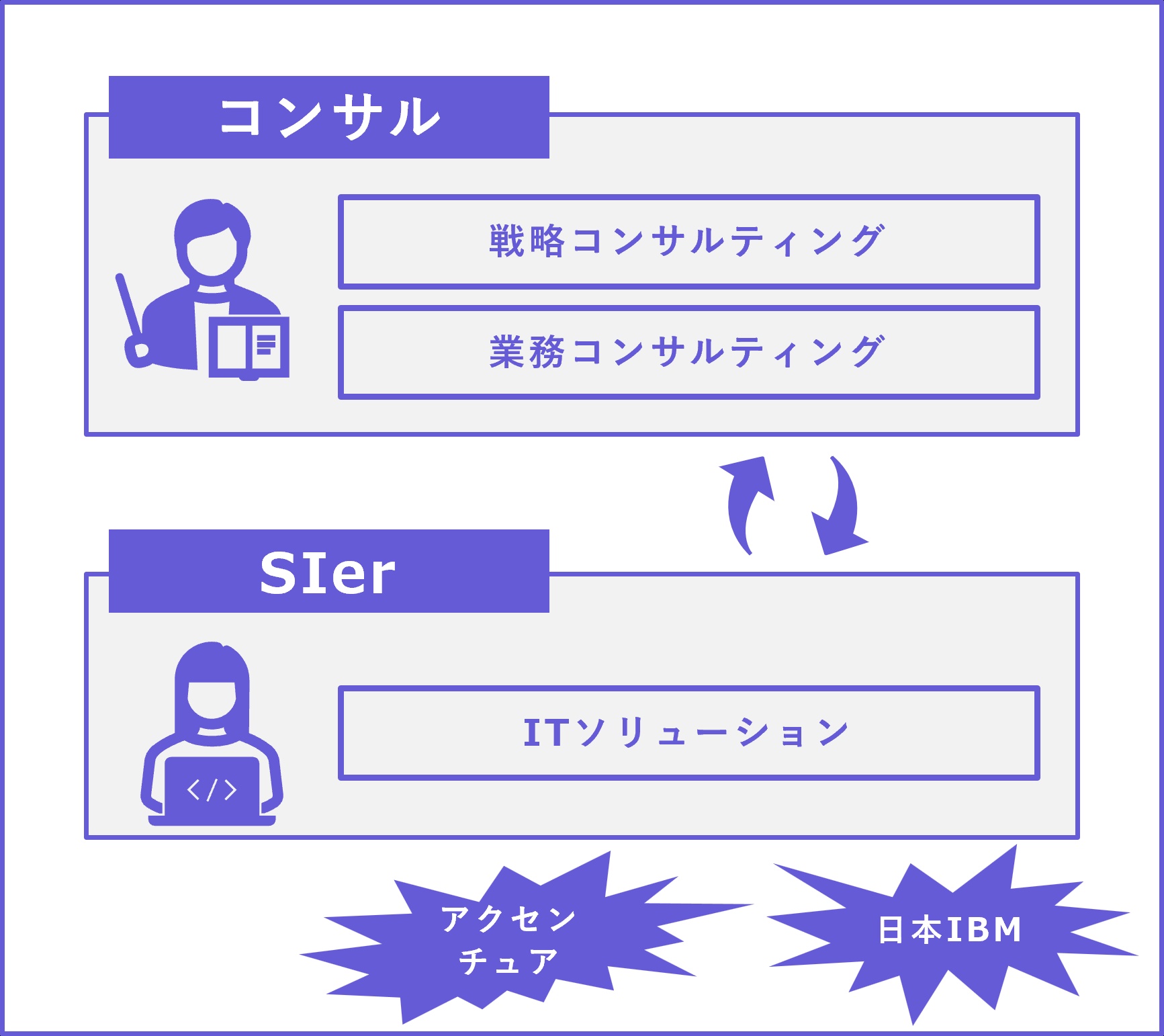
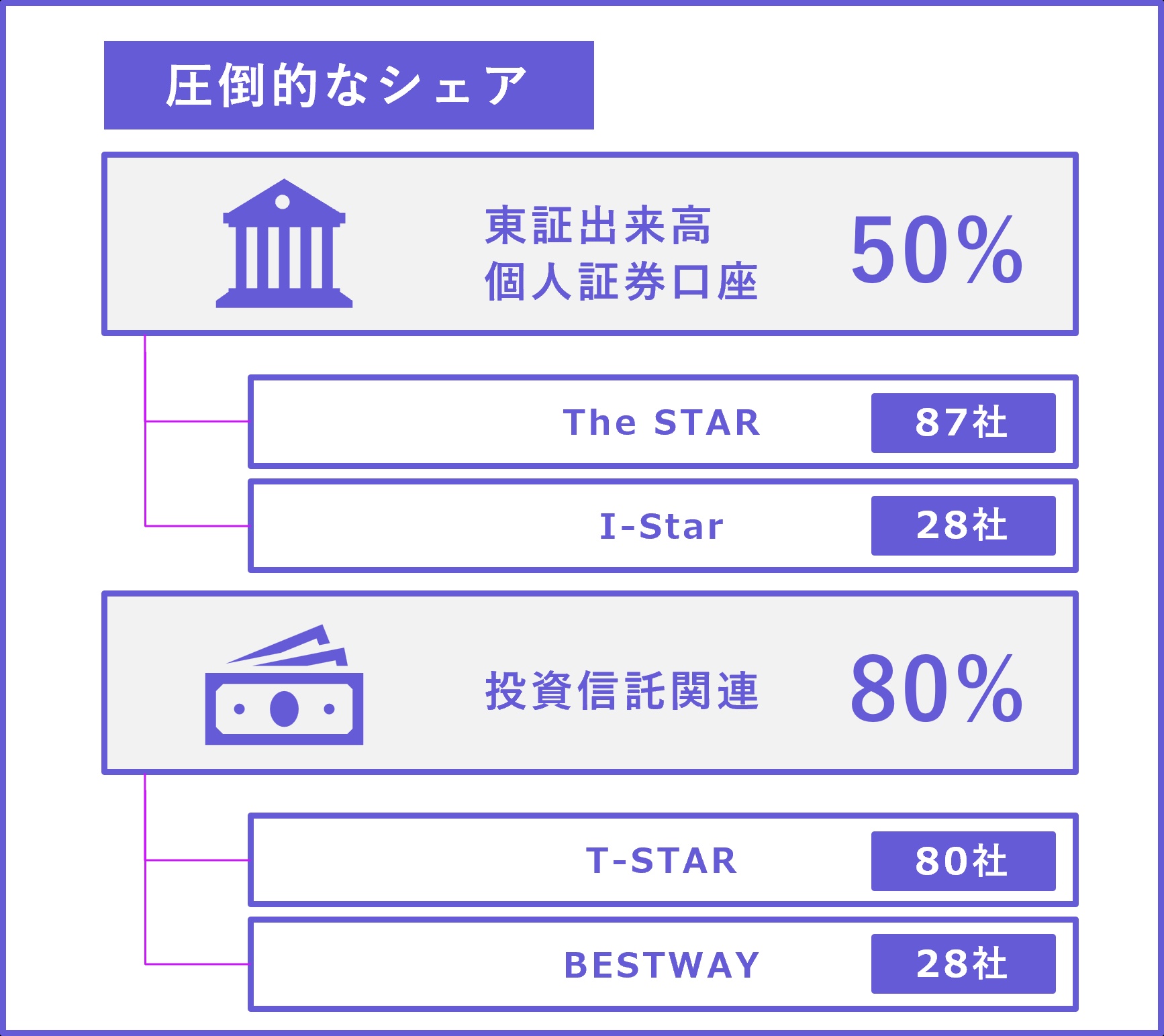
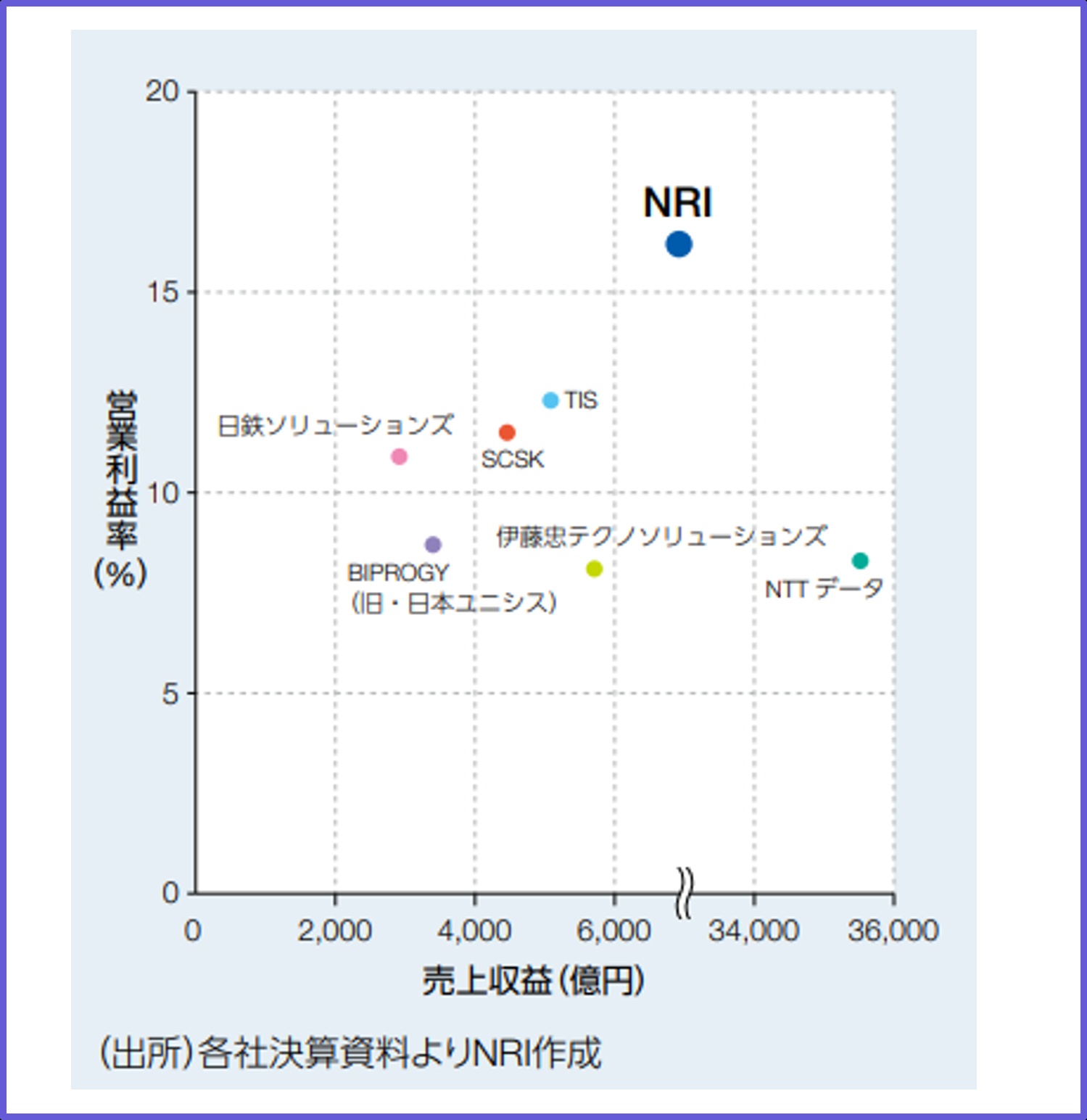
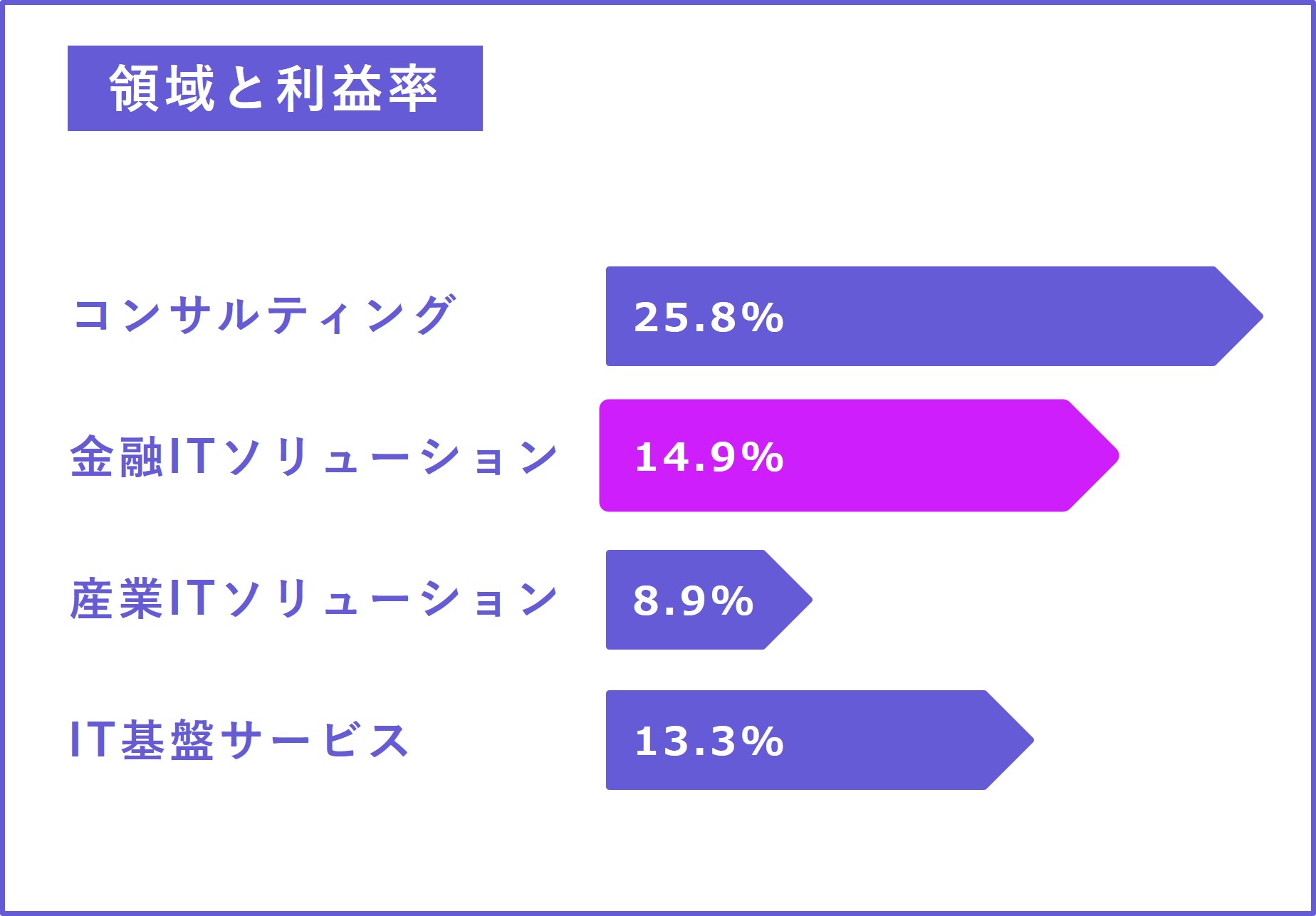
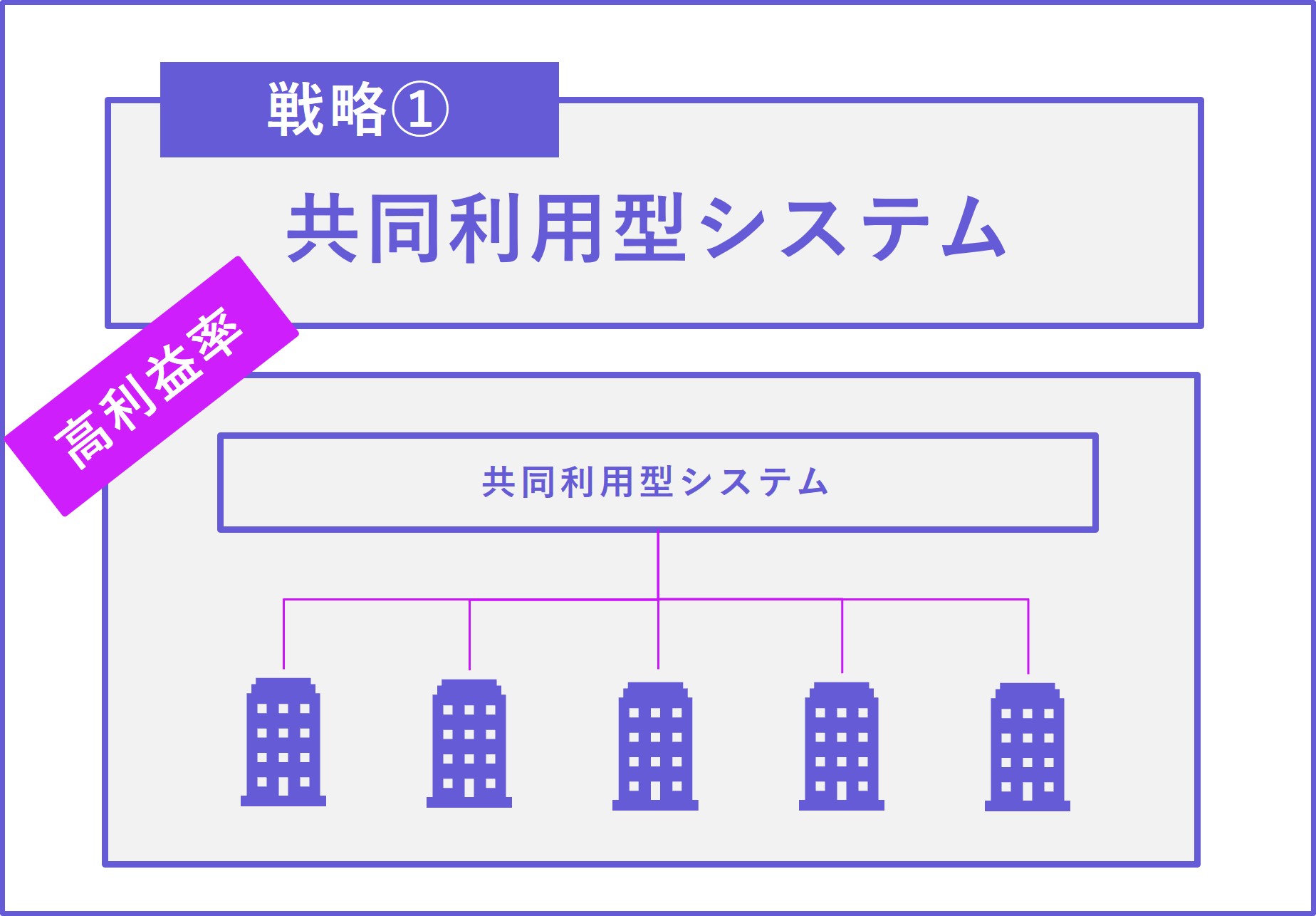
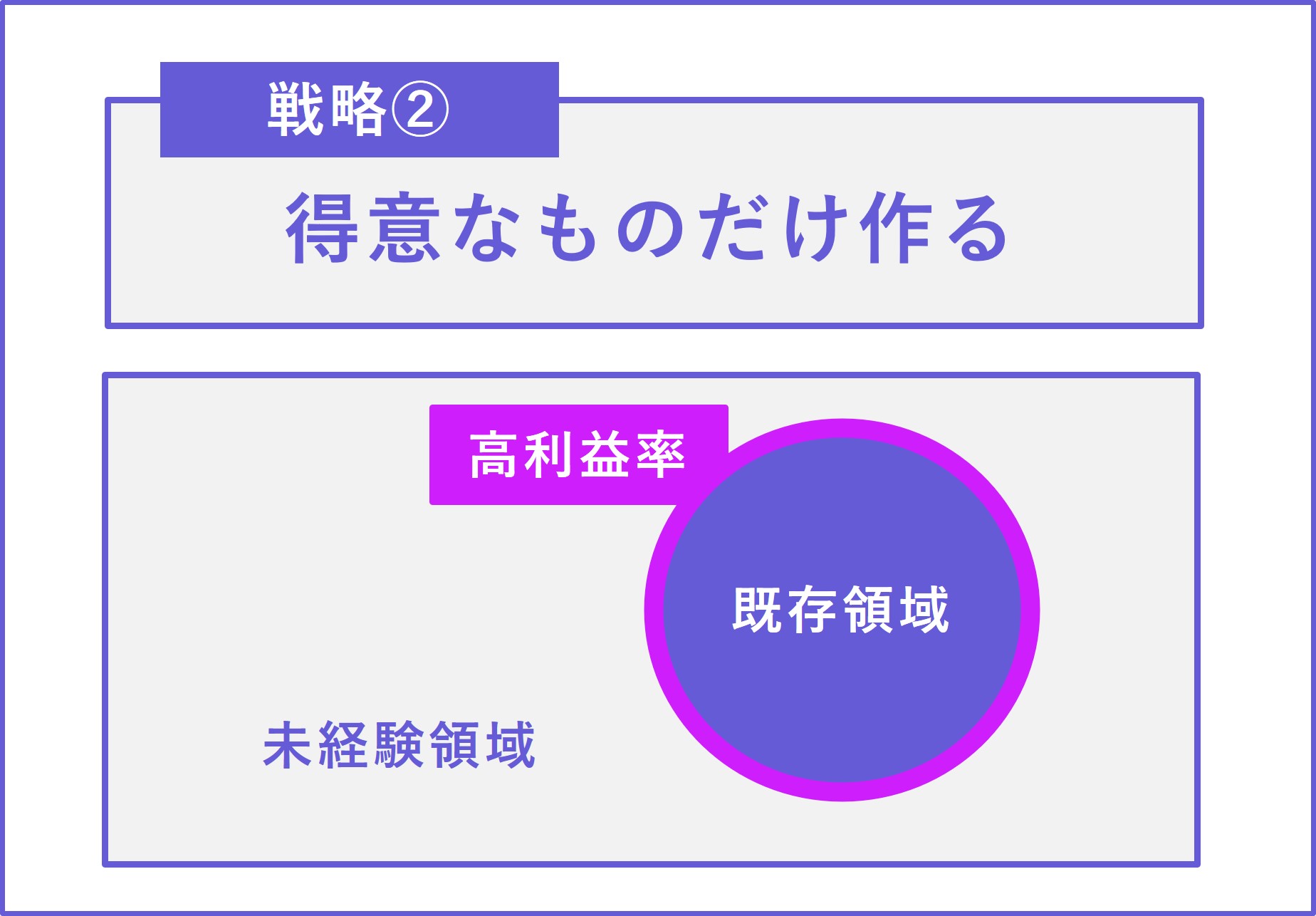
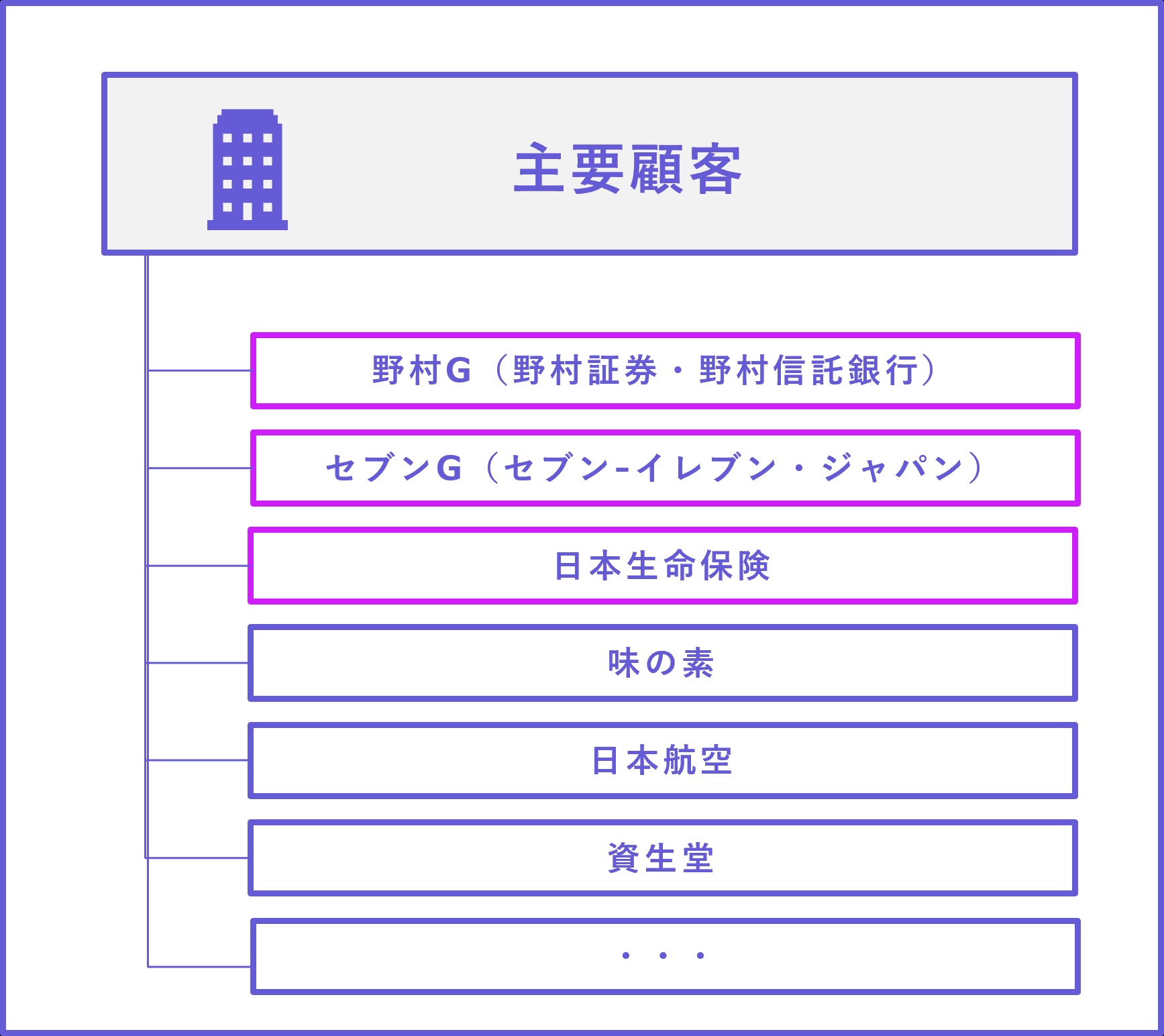
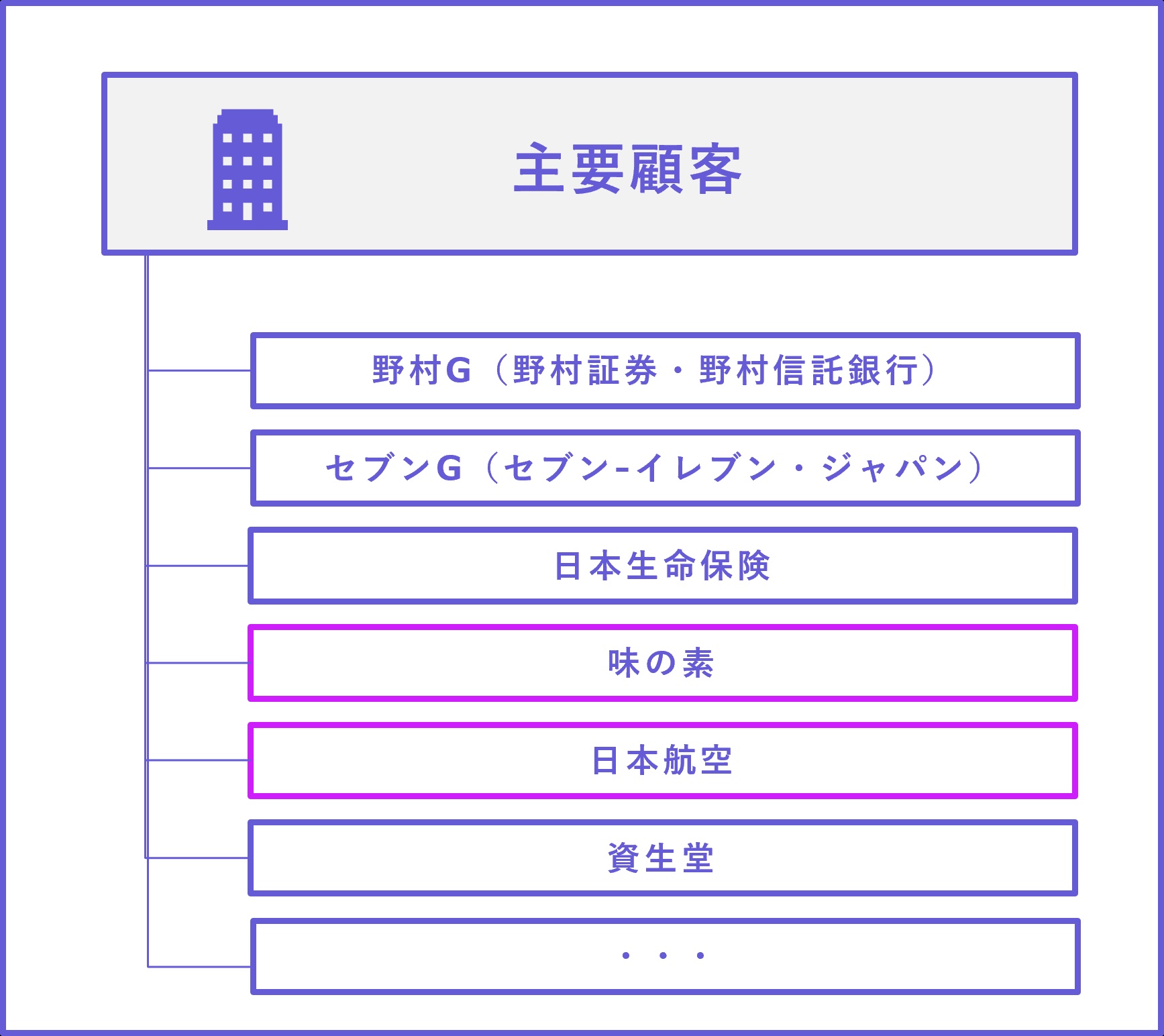
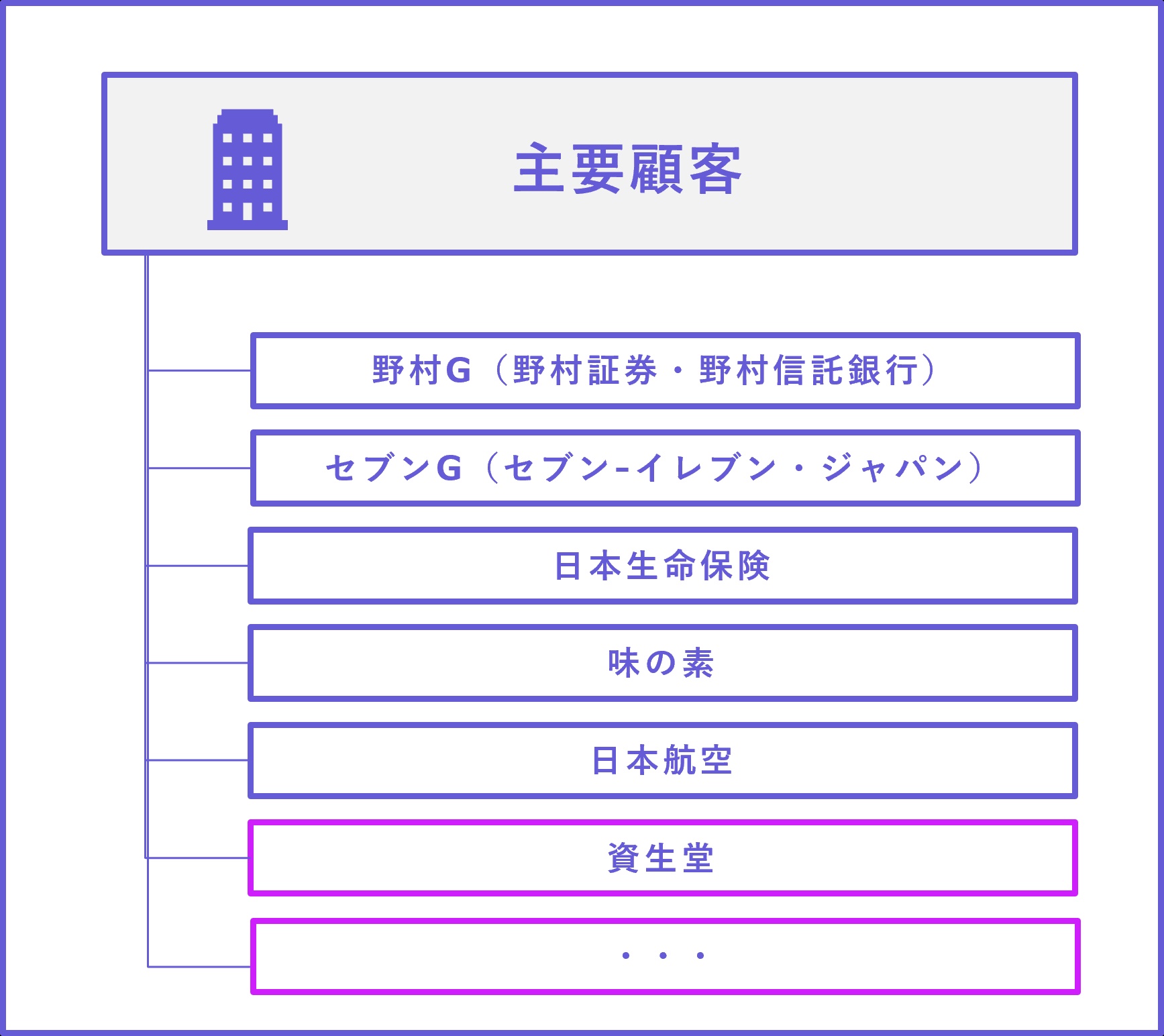
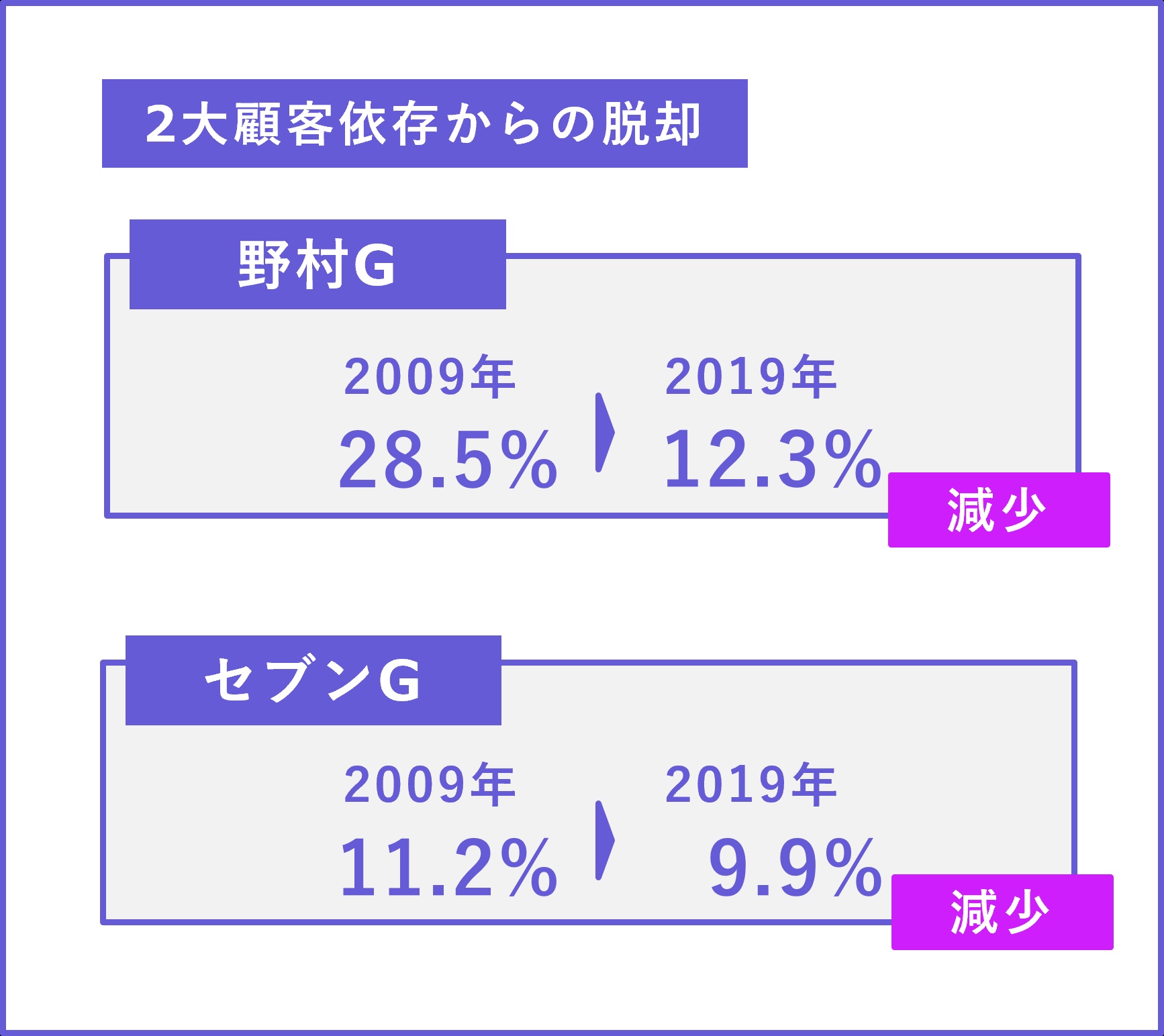
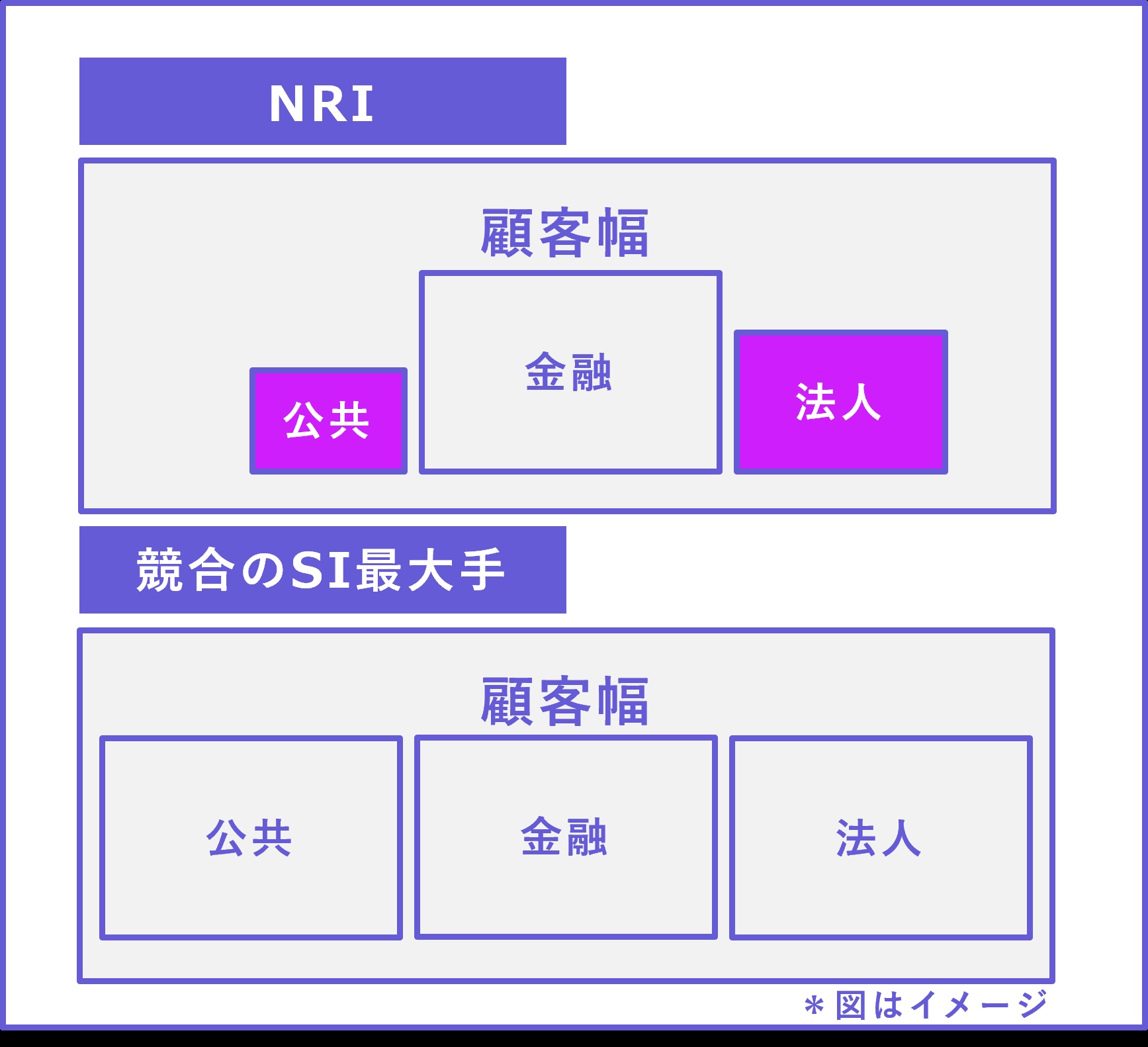
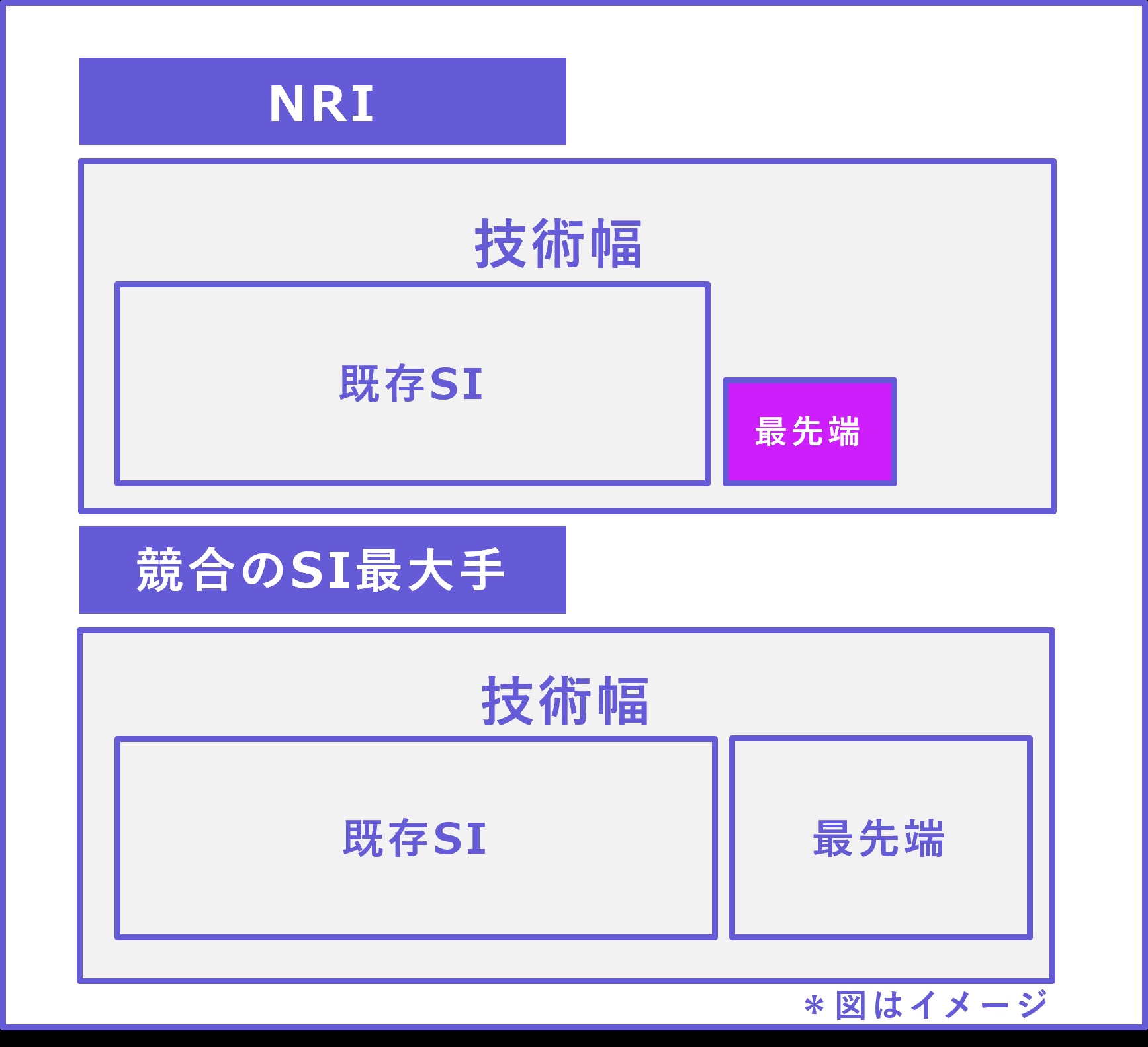
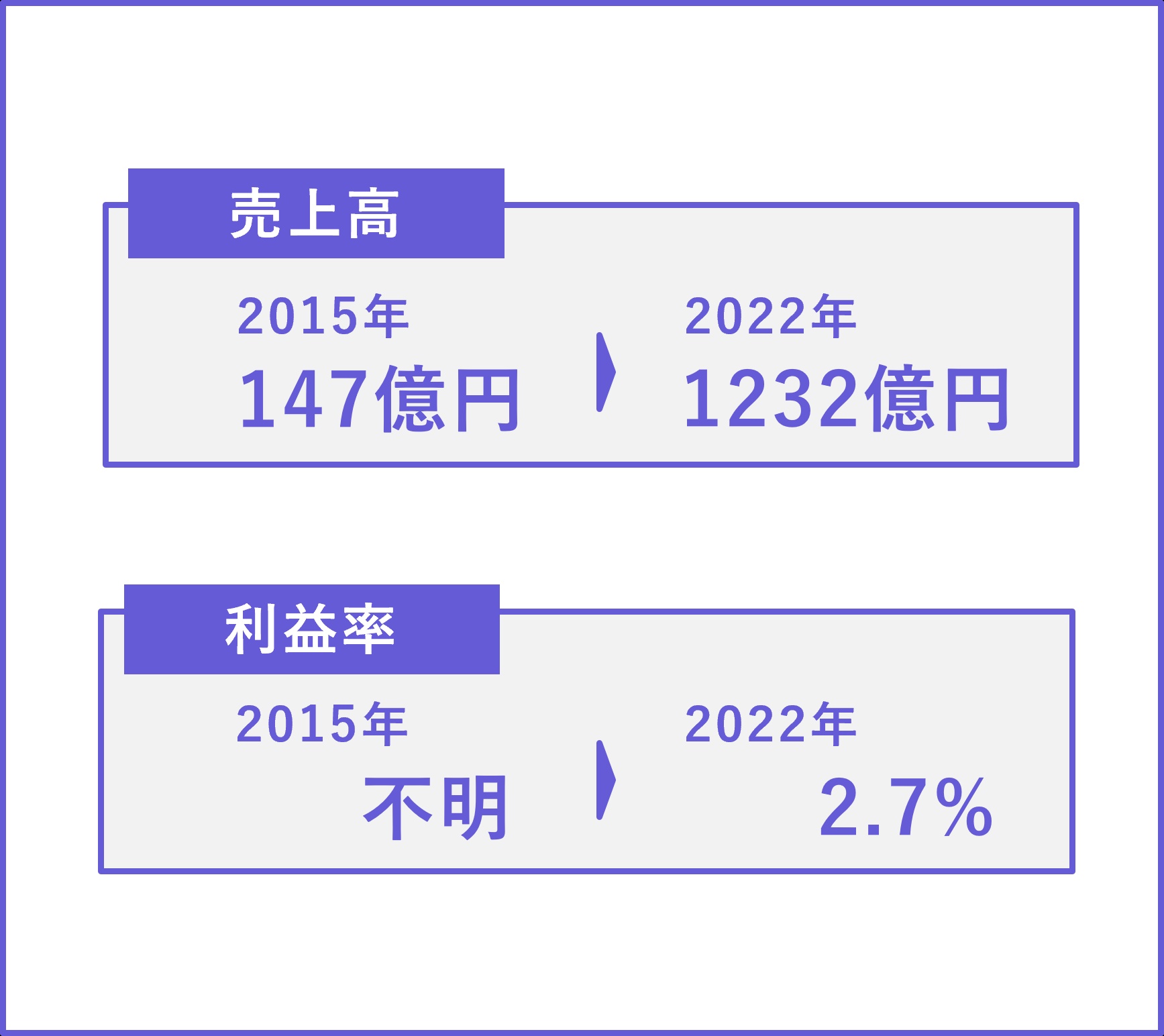
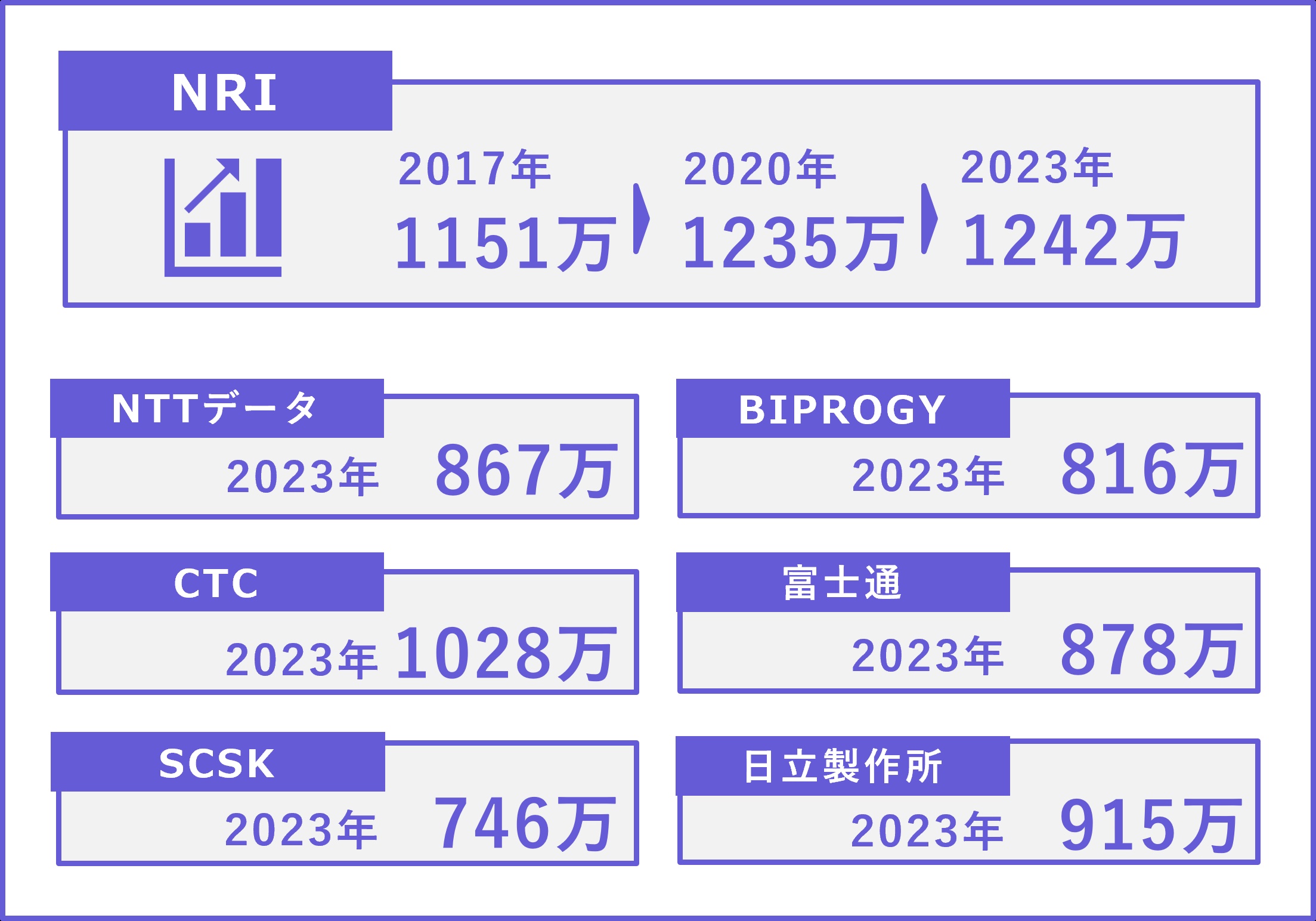
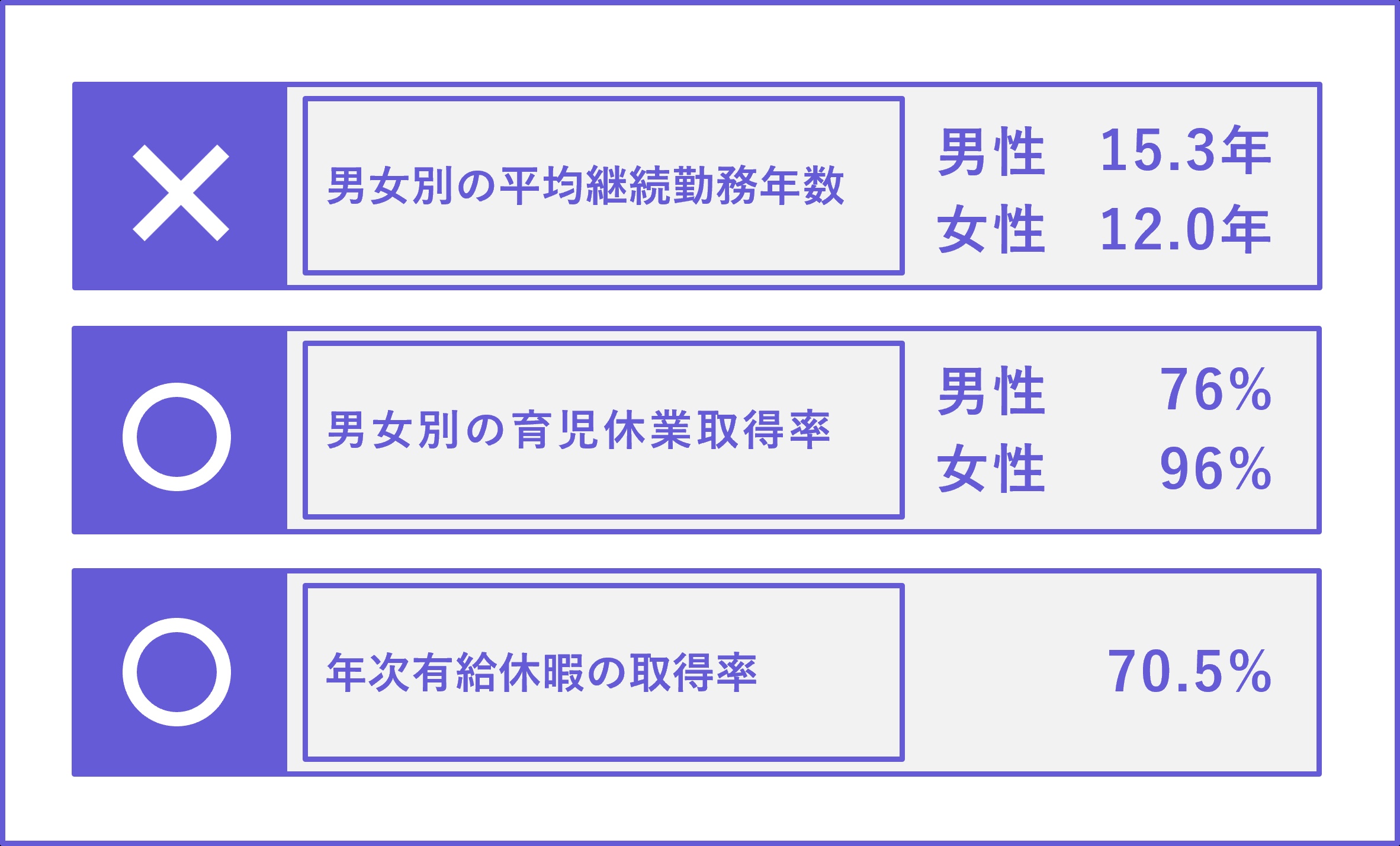
*大手SIer売上上位13社内の順位。